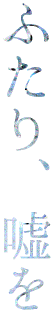「おはよう、ルイリ」
2
「水魔の私が、返せる言葉はないよ」
3
「この子は、フィーア。俺の弟子」
4
じゃあ、冬厄が去ったというなら、
水魔はどうなった?
5
「むかしにした約束を、
いまでも守ろうとしているくらい」
6
「もう、逃げないでね」
真夜中の森を抜け、やがて辿りついたのは、懐かしい呪術師の家だった。私の生きる湖からも遠く離れてはいない地に建っている、夏の棲家。
水底より生まれいでて、そしてルイリに初めて招かれて以来、何年も。一度とて欠かすことなく、夏になるたびに訪れているそこは、村や街といった人里からは少々の隔たりがある。あえて、いわば人の世界と、水の世界とのあわいとも呼べる位置に据えられている。
幾代か前の水の魔物を迎え入れるためにと、昔々に呪術師たちが作り上げ、そして代が変わっても放棄されることなく、百年以上を森の端のこのひらけた場所で受け継がれてきた家。空に花咲く茅葺きの屋根も、白い漆喰の壁も。ふるび寂れてすらいるが、愛情をもって何度も手を入れられているすまいは、私にとっても大切な場所だった。
さて、真夜中をだいぶまわった頃にこの棲家へと帰りついた私たちは、招き手である呪術師のもの、招かれた水の魔物のものと、それぞれに定められた部屋へと早々に別れ入った。
水魔招きの夜は、いつだってそうだ。儀式めいたことは、私が湖畔でルイリの手をとった時点で終わっている。
ゆえ、疲れ切っている私たちは、それぞれにしつらえられた部屋ですぐに水魔招きの異装をほどき、そのまま寝衣に着替えて眠ってしまうのを、儀式の夜の常としていた。
水の境界に接すること、あるいは夜半に森を抜けきることは、それぞれに消耗が激しい。
だからだろうか。しつらえられた窓からさしこむ陽で目覚めた時はすでに、朝も遅い時刻だった。
とどいてくる朝食のにおいからして、ルイリはもう起きだしているらしい。ともすれば、私よりも疲労しているだろうに。あわててとびおき、衣装箪笥にとびつくと、招きにあたって例年通りに用意してくれていた衣服をひっぱりだした。
選び取るのももどかしく、目についたワンピースをまとうと、私は背に流れたままの金髪もまとめずに台所へ急いだ。
けれども、廊下でかちあったルイリの姿に、私はどうやらその必要はないらしいことを知る。
「サリエ、おはよう」
「ああ、うん。おはよう、ルイリ」
あわてて出てきた私とは違い、きちんと装った青年は、まだだいぶ眠そうだった。
「朝食、フィーアに任せていてよかった」
しかし彼に劣らず、私も目覚めかけであったらしい。食卓のしつらえられている部屋へと向かいながらこぼされた言葉に、昨夜家に帰りついた時に言われたことを思い出した。
いわく、今年はルイリだけでなく、この冬厄のあいだに新しくとったのだという彼の弟子もこの家にて暮らすのだと。
家に辿りついたのが真夜中もだいぶ過ぎた刻限だったため、まだ対面してはいなかったけれど……そうだ、確かに聞いていた。よく家事をこなしてくれて助かっている、出来すぎる弟子だと。けれど人の間のいざこざのせいで、いまも呪いをわずらっているから、なにかあったら気をつけてあげてと。
言われていたことを慎重に思い出しながら、先に扉をくぐったルイリに続く。私たちの気配を察したのか、奥の台所の方から落ち着いた声で「おはようございます」と声がかかった。
声音の主は、言いながらこちらへやってきていたようだ。ルイリとくらべるとだいぶ背の低い姿がその腕に食器をかかえて、食卓をはさんで私たちの前にあらわれた。
幼さののこる容貌のそのひとは、私が背に流しているそれよりももっと明るく、もっと長い金髪を、ゆるく編んで刺繍入りのリボンでまとめた、十三、四ほどのこども。
「師匠、こちらの方が、おっしゃっていたお客人ですか?」
若草色の布をたっぷりと使ったエプロンを白いシャツの上から身につけるそのひとは、すぐに私に気づいたようで、ルイリと似たすみれ色の眸をかるくまたたかせた。
「そう。サリエと言うんだ」
かるくうなずいて私の名を告げたルイリは、次いで私に「この子は、フィーア。俺の弟子」と、うつくしい顔立ちの、細身のこどもを紹介する。するとフィーアは「はじめまして」と、たおやかに身を曲げて、挨拶の礼を私へとった。
「どうぞフィーアと呼んでください。サリエ殿」
「フィーア? その呼び名で、いいの?」
弟子。呪術師の弟子というには、その物腰はいくぶん洗練されすぎているようにも思えた。それに、フィーアの示した愛称も。あまりにつよく、フィーアが身にまとう呪いとまじないの気配にも。私はいくつかのことを、すこし怪訝に思いながら尋ねた。問いに、フィーアは少々戸惑ったようだった。一拍をおいてから返答する。
「ええ、フィーアと。略称ですが」
あわく微笑んで手にした食器を食卓に置いた弟子のこどもは、それにしても、と続けた。
「ご婦人だったんですね。師の話では、ずいぶんと親しいご友人と聞いていましたから、てっきり殿方かと」
「ルイリは、私のことを男だと?」
「いいえ。ただ、いままで師が他の女性と親しくされているのを、あまり見たことがなかったので」
そこまで言ったところで、フィーアは言葉をにごす。ちらとルイリにその視線が向けられた。
「サリエといるのは、好きなんだよ」
「そう、でしょうね。私にサリエ殿のお話をされていた時も、ずいぶんと、その、しあわせそうでしたし」
フィーアに告げながら、ルイリは既に用意のすんでいる食卓の席についた。あらためて目を向けてみれば、朝食であるというのにずいぶんと手がこんでいる。
ごろりと野菜の浮かぶあたたまったスープや、もとは大きな楕円だったのだろう、切り分けられたパン。
そえられた幾種類かの葉やハムの切り落としは、感覚からすれば一年ぶりに目にするごちそうだ。
「どうぞ、サリエ殿も。私も、ご一緒させていただきますね」
たしかに、このひとが家事をよくたしなむのだという、ルイリの言は正しいようだった。
ありがとう、よろこんでいただかせてもらうよ、と。そう言いそえた私は、久方ぶりに人間の食卓へとついた。
material and design from drew