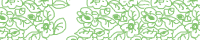常々、屋敷中を飛び回っている侍従烏の姿は見えない。瞠を招き入れると、七宮は「失礼にはなるでしょうが」と断って、使い古された長持に手をかけて、
「瞠さまが探しておられた暦……記録を、わたくし、隠しておりました」
「……は?」
ほうけたように声を取り落すと、七宮はさみしげに、語り口をひらいた。
「わたくしの生まれは、お父様が臣下の妻を奪ってのことなのだそうです。ゆえ、元来家中でも疎まれた身でした。ですから、由姫さまが西領にお嫁にいらして、その手元に引き取られてからずっと、血縁はなくとも、わたくしはかの方を、母と慕っておりました」
続けながら、七宮は長持の蓋を開く。そこにあらわされた紋は、森の広がる東領の、稔招ける霊狐の稲穂紋。そして、由姫の女紋。譲られでも、したのだろうか。
「由姫さまは確かに焼畑の記録を散じさせ、故郷東領の稔りを廃そうとされたのだと、おもいます。なにゆえそうしたのか、わたくしにはわかりません。そのようなことをしていたと、由姫さま自身から告げられたこともありませんでしたもの」
瞠には、わかってしまった。口元を引き結び、無意識のうちに膝の上でこぶしを握る。
賢い四宮由姫は、東領を呪っていったのである。家の力を、領のみのりごと削いだのである。彼女は縁を切り捨てた。守るべき民を選ばずに、実家の威信を選ばずに、ただ世にあかされぬ我が子を選んだのだ。彼女は――母は。
「ですけれども、交わしたお文や、聞かせてくださる東領の話に垣間見た不自然さや……とにかく、由姫様と焼畑が関わった時に違和を感じる事は多かったので、以前よりなにごとか、みのりに手を加えようとしているのではと考えておりましたの。ゆえ、境の坂井に参じた折に、妹君さまに尋ねて。そうしたらみのりに害為す意思があって、なにやら行動はされていたようだと、聞いたのです」
長持からいくつかの衣を出す手を休め、七宮は一呼吸をおいた。並べられた着物は年若い姫君のものにしては、真新しい品があまりに少ない。
「母と慕った由姫様の、知らずにいた恐ろしさを垣間見た気がしました。気が抜けて、泣いて、心細くて、ただひとりがこわかった。そうしたら瞠さま。あなたがここに、いらしたのよ」
「私が?」
「ええ、あなたが。はじめて、おなじ獣返りの方に会ったわ。それだけで、うれしかった」
そうわずかに微笑む七宮と彼女の手を、瞠はただ視線も動かせずに見つめる。
「……お会いした時、あなたはそう弱っているようには見えなかったが」
「だって、東領の主筋の御子様方は、どなたもわたくしより年下だもの。この角が成長しきるために、本来ならば体へゆきわたるべき養分が奪われていたのでしょうね、こんな幼いなりでも、数えでもう十七。きちんと姉君らしく振舞いたかったわ」
――それでも、後にとりかかったのは、焼畑の記録を、こうして隠すことでしたけれども。
手をのばして、瞠は中を改める。間違いなかった。けれどもどうしても、目の前に座す人がいまにも崩れ落ちてしまうのではないかと心配で。彼は記録書を手にせども、その場から立ち上がることが出来なかった。七宮は七宮で、いままで随分と感情をはりつめていたのかもしれない。ぽつりぽつりと、取り落とす声がとまる気配はない。
「由姫様の呪いを知っても、それを止めようとの気力なんてなかった。むしろわたくしは、その呪いを確固たるものにしようとすらして、書物を隠しました。だって、由姫様がわたくしの妹を産んだ頃。角に枝葉が芽吹きだしたのを機に、わたくしの出自を疎んじていたお父様は、わたくしを廃嫡と処していましたから。西領の
獣返りを、異形と厭う。そのおぼえは、瞠にもあった。
「枝が伸び、葉が落ち、異形が雄鹿の角の形となって、獣返りということが瞭然のものになっても、もはや居場所などなく。なにせここまで顕著にあらわれれば、古い聖性の形とはいえ、今の世では乱れさえ招きますもの。ゆえに、由姫さまが異母弟を産んだ床で、儚くなられ、それを期に父に命じられた坂井入りとても、夜陰に乗じての密かな旅路でした。いつか憧れた、嫁入り行列などとは無縁の道程。けれどそれでも、もうよかった。なにせその時わたくしのてのひらには大切だと思えるものはもはや、思い出の抜け殻しか残っていなかったのですから」
「七宮どの」
こぶしを握った瞠は、うつむきがちに視線を落とす七宮の顔を、どうにか晴れさせることかなわないかと覗き込んだ。その眸を、垣間見るだけでもいいと思った。
「いつのまにか角を飾るは、枝葉の青から黄の花となっていました。
そして覚悟を決めたように、七宮は面をあげる。
交差した視線のつよさに、むしろ瞠の方が戸惑った。
「でも。瞠さま。わたくし、あなたと暮らして、人に
「嬉し、かった?」
瞠には、彼女の告白を、うまく理解できなかった。あんな、純粋なだけではない言葉の数々を喜んで。曖昧で脆い不明瞭な理由で、彼女は暦を隠したのか。
「そんなことで、あなたは――」
ほうけてこぼすと、七宮はいたましく、笑う。
「そんなことでも。それでもわたくしには、生涯で一番、しあわせな時間だったのです。なにに代えても、なにを負っても、惜しくはないほどに。謝罪はできませぬ。たとえ瞠さまだとしても。……だってこんなことになっても、どうしてでしょう。悔いては、いないのですから」
言葉は奇妙なほどに力強くとも、笑みの奥で、七宮は泣きそうだった。隠していた書のすべてを集め、膝を立ててにじりよった彼女は、暦を、瞠へ手渡した。
「お持ちください、瞠さま。わたくしたちの祈りは、所詮、呪いだったのです。ほんとうに叶っては、ならなかったのですから」
その腕の中に託された書に、瞠はなんの言葉も紡げぬまま、ぎゅっと口元を引き結んで。しばしの沈黙ののちに、彼は西の対から
かくて境の鐘は、鳴る。東領から人を呼ばう為、六度、たからかに音を響かせた。