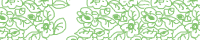しかしそれから幾日かけて書庫に眠る膨大な記録に触れようとも、目当ての暦は見つからず。
次第に焦りは苛立ちに代わり、わずらわしいばかりであった。
由姫は、なにをしていたというのだろうか。この、境の坂井で。あるいは東領の城の奥で。
『四宮は、確かに、嫁入りの際に境の坂井へ立ち寄った。しかし本当に、彼女は暦を奉納したのか』などと。疑い、誰に言うでもなく呟いたことも一度ではない。
「瞠さま、こちらの書は年代順に並べましたけれど」
「助かる。七宮どの、そろそろ休まれよ。だいぶ、量があっただろ」
「それなりには。ですけれども、まだ大丈夫です。そちらの分類も、お手伝いしますね」
さて、この午後とても、書庫に籠りきりの瞠を訪って、七宮は手伝いを申し出てきていた。そう多くの言葉を返さずとも、かたわらで笑む姫は、始終、楽しそうに振舞い続ける。
「いや、いいから。これらは東領の品。西領のあなたにたやすく触れられても困る」
そのような姿が、先よりの苛立ちと入り交じって、わずらわしかったからだろうか。
埃っぽい書庫の床に座し、必死に両手と頭を働かせて巻物を分け整える彼は、膝をかがめて声をかけてきた七宮に、やつあたりのように言い放った。ふとした時とはいえ、向けた言葉は、思いのほかにするどい棘だった。
「ごめんなさい」
はっと気づき、思わず顔を上げると、沈んだ面持ちの七宮と目が合った。
「それではわたくし、奥を見てまいりますね」
その表情が、なんとも言えずいとわしい。
境の坂井に参るまで、憶えたことの無かった情が、心中を
咄嗟に口を開きかけるも、どうにも、書庫の奥へ身をひるがえした彼女を呼び止めることはできず。彼は少女の背から視線を戻して、分類を続けた。
……七宮には、探し物については、焼畑の暦であるとだけ告げていた。身近くにて瞠を手助けしようとはにかむ姿に居心地の悪さをおぼえた彼が、詳しくは告げずに資料の分類を、巻物の出し入れを、題だけ告げた書の調達をと、都合の良いようにものを頼んでいる。それだけだ。
それでも、あのような顔を目にするなど、わずらわしい。
どうにも納得のいかぬ情が、苛立ちに拍車をかける。
荒い心を静めるかのように、瞠は膨大な量の巻物の選り分けに徹する。やがてそれに一区切りがついた頃。書をこれでもかと抱えて、もう一度、少女がこちらへ来やるのが見え、そして。
「七宮、どの!」
薄暗い書庫の中、わずかに足をもつれさせた少女に、瞠は反射的に膝を立てて手をのばした。しかしわずかに間合いが足らず、彼女の全身の体重が貧弱な肩に寄りかかってくる。抱えていた書の数々も七宮の腕から落ちかけたものだから、瞠の血相が変わったのは言うまでもない。
思いのほかに軽すぎる七宮の身にも、いいようなく胆が冷えた。
はずみで、七宮の角に咲く、黄金の花が視界をかすめる。
わずかに透けて、いかにももろい。
それでもなんとか支えきり、体勢を持ち直したとき。ふたりの顔色は完全にあおざめていた。
「ごめんなさい、あの、ありがとうございます」
声を震わせる七宮に、瞠は身の痛みも忘れ「どうしてこんなに」と彼女の抱えた書を示す。
「系図が出てきたのです。地図も、双領の史書も。東西揃ってのものなど、ここにしかありませんから――瞠さまにもお見せしたくて。息抜きにでも、と」
「系図?」
なるほど、書の合間には二、三の巻物もまぎれている。示された興味に、七宮はすこし表情をあかるませ、手早く瞠と、そして己の膝の前に開いてみせた。
「そうなのです。ええと……これ。ここに、お父さまがおります」
そうして、和議が成って以来のここ数代の部分へ、瞠の視線を導く。
「東のご領主さまは、こちら。瞠さまはまだ書きこまれておりませんか」
それなりに近しい年に編纂され、納められたのだろう。和紙も墨跡も、そう古いものではない。それに、その筆跡は記憶が正しければ――四宮、由姫の字である。
「お名前が書かれるとしたら、この下ですね」
嫁ぐ前にしたため、そして納めて行ったのだろうか。わずか呼気をつまらせる瞠のかたわらで、彼女が指をのばす先は、養母と叔父の名から出でた、従姉の名の隣。どうにも面白くなくて、瞠は「ちがう」と否定した。そうして、西領領主と由姫の名の間を指す。
「あなたの名は、ここだろ? 東領から嫁した四宮と、西の当主の姫。そして、私が系図に書き加えられるとしたら、こちらだ」
嫁いでゆき、所属が変わったことを示す一本の線。その先に記された四宮の名の下、父の名など書かれていない場所に、瞠は指先をすべらせた。従姉の名は母の字で書かれてはいたが、とうぜん瞠の名は系図には無い。認められなどしていないのだ。母親にさえ。
すると七宮は驚いたように顔を上げる。その様、尋常ならざるほどだ。彼女はおおきくみひらいた瞳で、じっと少年を見つめてきた。
「瞠さまは。瞠さまは、それではお
「……そう」
嘆息まじりに顔を上げて七宮を見れば、彼女は。安堵して力が抜けたような、背負っていたものを取り落したような、けれど何かを成し遂げたような感情を、その顔に浮かべていた。
「いまさら、やはり姉妹ごっこがしたいとでも? いやだよ、私は。兄妹馴れ合って親しむなんて、烏どもでじゅうぶんだ」
異父とはいえ、兄と妹であるとあかした瞠へ、この娘はなんと言うだろう。わずかに眉根を寄せた少年を見つめ、七宮はしかし、言葉の代わりにそのまなじりに、じわりと雫を浮かべる。
「ちがうの。ちがうのです」
そうしてしばしの呼吸をおいて後。ぽろぽろと浮かんでは、袖に落ちる涙を右の手でぬぐって、七宮は左の指先で系図を示した。
「わたくしは、ここ」
どうしたことか。七宮の指先に、由という、瞠の母の名はなく。
「瞠さまが、四宮さまのお子であるなら、親しく兄弟だなどと、呼べませぬ。わたくし……顔も声もしらずとも、一度はあなたを憎みも、したのですもの」
代わりに西領の領主の名の下に、不義の関係の子と表すように、母親の名もなく女子、と。ただそれだけ、記されていた。
異父の妹ではなかったのか。驚きとともに七宮を見れば、彼女は瞠へ、はりつめた声で言う。
「瞠さま。きちんと聞いて、いたのです。あなたのお母さまから、四宮さまから。故国にのこした
堰を切ったように言葉を連ねるひとの、瞳に浮かぶ意志は、つよい。
「いらして。西の対へいらして、瞠さま。お願い。あなたが焼畑の暦を望み、そしてあなたがわたくしの探した御方である以上。わたくしのわがままは、あかされるべきなのです。夢など見てしまった
そして少女は、書庫に広がる書物の数々もそのままに、少年の手を取って立ち上がる。
七宮に手を引かれるがままに、瞠は西の対へ足を踏み入れ。その先で――彼は己を捨てた母の呪いを、垣間見た。