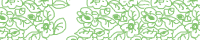境の坂井に仕える侍従であるという兄君は、瞠が性別を偽って神域に参ったことをなにかしらとがめでもするかとは思ったが、案外にそのようなこともなく。今にして思えば、もしかすると門前で名乗り上げた時に既に、気付かれていたのかもしれない。それほどに、わだかまりを示さずに、日々を屋敷中の手入れにあけくれて過ごしている。
それにしても、そういった仕事、たとえば朝夕に屋敷の
不可解であるといえば、七宮である。
あのように手荒に言葉を浴びせたというのに、七宮はどうしたことか、瞠を恐れも、疎みも、厭いもせず、ただ穏やかに接してきたし、しきりに言葉を交わしたがった。
それなりの時間を共に過ごせども、始終、行動を共にするわけではない。七宮が朝の早くに境の坂井――屋敷の奥まったところにまします、三宮の古井戸の手入れに赴くときなどは、瞠はただ彼女を見送るのみである。
古くに時代をさかのぼれば、三宮……つまりはあがめられるべき対象である古井戸に触れられるのは賢い彩宮のみであった。時が下った今とても、この井の聖なる水に仕えるのは、もっぱら彩宮と、そして獣返りの役目だと聞く。
獣返りをかたる、女ならざる瞠である。さすがに、境の坂井にまでは赴くことはなかった。
さて、坂井に入ってより十と幾日目かの宵。
『嫁入り道具』の中にまぎれさせた、養母からの手紙を読み返したのはそのような頃だった。
坂井入りした時分よりも秋は深まり、徐々に風が冷たくなってきている。着物を一枚多く着こむようになってから、表に出しておく衣の枚数は足りなくなっていた。
ひっそりと手に入れ、今まで長持の底に隠すように仕舞いこんだままだった数枚の男物の衣を取り出しながら、瞠はそれにしても、と思いを巡らせる。
ともに城の奥に籠められ続けた母が去って以来、養母の手元で育てられるようになってからは、「姫君」として装い、「姫君」に扮し続けた。それゆえ、この俗世から隔てられた境の坂井においていくら自由に男物を纏えるようになったとはいえど、常は小袖と袴ですませている。着物に対する不慣れさと、資料に向かう時間を割いてまで、長持の奥に隠すようにして持ち込んだ衣を取り出すことのおっくうさのせいだった。
目当ての着物のいくつかを、侍従烏の兄君の手を借りて、日ごろ使えるように整える。そうしてから、着物とともに長持の奥から取り出された一枚の手紙を慎重に開いて、彼は記憶に誤りがないかと目を通した。
懐かしい
「瞠どの、それは?」
「我が東領の彩宮から、境の坂井に眠れる資料の写しが欲しいと頼まれて。これは、必要な部分を書き付けた記録」
示すと、かたわらに座していた兄君が手元に広げられた和紙を興味深げに覗き込む。
記された年号と、数字と文字の羅列。意味はたやすくはわかるまい。しかしこの記述こそが、東領が豊穣を求める、理由そのものであった。
「焼畑の記録を調べてほしいと頼まれたから、私は坂井に参った。この神域の屋敷には、代々の賢しき彩宮たちにより、双領の記録の全てが奉納されるのがしきたりだから」
じいと視線を動かさない兄君に、瞠は語る。
東領ではより豊かな稔りを求めようと、数年に一度、耕作の間を縫って、領主一族が焼畑の指揮を執ること。領中の畑に順に火をかけては土の稔りをよみがえらせ、より多くの稔りを願うこと。その周期は、過去の記録を積み重ねてつくられる暦に従うのだが……しかし十数年前からのある数年の間、記されていたはずの暦が抜けているのである。
暦を綴る役割を担っていた瞠の母が、実家に記録を残さずに嫁いでいってしまったのだ。
「いわくに、『
そらんじると、兄君は「それほどまでに欲するということは」と視線をあげずに尋ねる。
「欠けのある記録からの暦づくりは、結果が芳しくないのですか」
「らしいな。万一、この先に膨大な量の計算式を仕損じてしまえば、貧しい山辺の豊穣はゆうるりと去る。宮の威光も、領主の権威も翳ると。そのように仰っていた」
ゆえに坂の境に参って以来、探し続けたのはこれに関わる資料である。しかしながら、こうして探し続けてさえ、ここ十数年の記録ばかりが、まったくみつかってはいない。
「領内すべての畑とその地主を把握し、収穫と周期を突き合わせ焼く畑を割り当て、ですか」
ようやく顔を挙げた兄君の言に、瞠は確かに、と頷いた。
女は先々まで、やはり未来を読んでいるもののようだ。たったひとり、おおやけに東領の跡取りと認められている瞠の従姉姫を、境の坂井へやるわけにはいかぬ。神域に参るということは、俗世から一度縁を切るということだ。形だけ、一時のことだとしても、跡取りは失えぬ。
かといって領主の正室である六宮が、やすやすと神域へ赴くわけにもいかぬ。
ならばいまや身動きの叶う領主の血筋は、瞠の他にはない。ゆえにお互いにとはいえ利用しあった結果、養母は瞠を、由姫亡き後にこの齢まで育てたのだろう。万一、従姉が坂井へ赴く以外の手段がなくなった時、瞠が東領を継げるように。さりとて、結果は真逆ではあったが。
「女はこわいな、兄君どの」
「然様ですか?」
指先で書付をもてあそびつつこぼしてみれば、兄君は意外そうに瞬いた。
「こわいじゃあないか。母上も、養母上も、七宮も。みな、裏で考えることを、男にはつまびらかにしない。どころか、笑みの裏では時に都合よく利用さえしようとする」
そうだ。思えば母も、何事か東領に害為そうと、企んでいたようだった。七宮だって、最初にあれだけ拒んでおきながら、なおも親しげにしてくるのである。奇妙な違和ばかりを憶えてはいたが、なるほど。裏ではどんな計略の糸を繰っているのやら。
すると烏は心を読んだように、朗とした笑みでもって軽やかに言った。
「尋ねれば告げてくれますよ。その日何があったか、誰とどんな話をしたか、心の内ではどう思ったか、いかなることを考えたか」
「妹君もか?」
近しい人こそ、その心の裏側に、なにごとか抱えているのは感じとれる。
ならばと兄妹の名をあげてみれば、少年の笑みはますます楽しげに深まった。そうして、思いがけぬことをつきつけてくる。
「ええ。たとえばあなたがたがめぐりあった日。彼女は我が
その言葉に一瞬、身構えたからだろうか。続く声に、口元をぎゅっと引き結んだものだから。
『わたくし……殿方に間近でお会いするの、初めてなのです。どうしましょう、妹君さま。どう、言葉を交わせばよろしいのかしら』
予想もせぬ言葉に、瞠は嘘だろ、と眉根を寄せた。
兄君は、にいと目を細めると、楽しげに言う。
「人にあかさずに謀ること、みなみな、おそろしいものとは限りませぬよ」