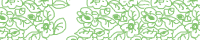城下からは
世は乱れがちだと伝われど、ここは辺鄙な山奥の小国である。山岳の他に隣り合う西領とは数代前に和議もなされ、今や相争う相手もいない。なれば古い慣習に立ち返り、囃子は祝い、祝いは加護と喜ばれる花嫁行列へ、身分の高下を問わずに声が響くのも無理はなかった。ならいのとおりの祝いであれば、とがめられることもない。
だから、行かないでなどと。
そんな祝いではない言葉は、嫁ぎゆく姫に、向けられてはならないのだ。なにせ、彼女は瞠にとってだけでなく、この国においても大切なひとなのだ。抱える知恵と知識において、
ほんとうはそんな彼女の嫁入りを、異形の瞠は祝わねばならない。
瞠は、先祖の性状が色濃くあらわれた、人ならぬ獣返りの子である。そう言われている。
同じ神域を重んじ、同じ御山の神を奉ずる東西の双領の一帯では、時折その身に自身の
領主一族の御祖に、その見目まこと似通う、こども。そのような、
「ひとりになっちゃう」
母とは二度と会いまみえること叶わぬと、今や養母となった叔母に告げられても、である。だってそんな言葉やならわしに、黙して従い耐えられるほど、瞠は大人ではないのだ。
「お嫁になんて行かないでよ、母上……」
涙にまみれた
『ねえ、瞠。この先、東の土地から稔りが去って行ったその時は、きっとあなたは、どこへだってゆける。宮の威光が、ひいては領主の力が翳ったなら、きっとあなたを無理に籠める必要も、余力も、この家からなくなるもの。そうしたら、瞠は好きなように生きられる』
そんな言葉を、別れ際、瞠の異質な
生き
東領嫡流の血を継ぐ獣返りのこどもは、嫁せる母の懐より手放された。