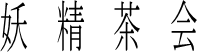
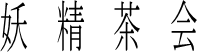
「お招きいただき、ありがとう。レディ・コーネリア・アディンセル」
「子供のためのお茶会(ナーサリーティー)へようこそ。応じてくださり光栄よ、トリストラムおにいさま」
透(す)くほどにあわい体を少しかがめ、トリストラムが少女へ挨拶をすると、濃茶の髪の幼い彼女は淡々と礼を返した。
子供部屋(ナーサリー)の主人、当代のアディンセル家のたったひとりの令嬢コーネリアは、どうにも冷めた子供である。トリストラムが生前に可愛がっていた、彼の弟モーリスや、死んでから見守ってきた、代々のアディンセル家の子供たちとはずいぶんとその性質を異にしている。そんな少女の冷淡さを、トリストラムは少しばかり惜しく思いながら、招かれた茶会の席についた。
「ねえシャノン。私、ちゃんとできた?」
すると待ちきれないというように、コーネリアは傍らに立つ金髪の、トリストラムの享年よりもわずかに若い少女へ、ちいさな声でこそりとたずねる。
幼い主人の傍らに控えている、妖精地帯出身と聞く彼女は、名をシャノン・サリスという。コーネリアの乳母(ナニー)が病に臥して以来、特別に乳母に代わって子供部屋の責任者として扱われるようになったナースメイドの少女。使用人でありながらも、誰より子供に近い立ち位置にある彼女は、女家庭教師(ガヴァネス)の教育をうける前の幼い子供たちをしつける役割も担っている。……すべては次の乳母が決まるまでの、一時的なものではあるが。
「はい。きちんとできましたよ、ネリー。――では今日は、自分で茶葉を選んでみましょう」
さて、この子供のためのお茶会も、そんなしつけの一環である。本来ならば人形を相手に、あるいは同じ年頃の友人を招いて、乳母の指導のもとで小さなお茶会を開くことで、将来の社交の練習とするのだ。もっとも、コーネリアが子供のためのお茶会をはじめて以来、招待客の座るべき席に、人形が置かれたことも、友人が招かれたことも一度としてないが。
なにせ彼らを招くまでもなく、お茶会の席に座りたがる者が一人、子供部屋には棲みついているのである。それが、このトリストラム・アディンセルと称される亡霊。死してなお、一世紀以上をアディンセル家の子供たちのもとに寄り添う、妖精の名づけ子。かつてのアディンセル伯爵の、早世した兄だった。
「……トリスの方が、選ぶの上手じゃない」
「でも、ネリー。これも練習です。それに難しいことは言わないから」
不安さを帯びた言葉にも、シャノンはかたわらのティーカートから、紅茶を保管しているキャディボックスを手に取った。そしてコーネリアに差し出すことで、たやすく声を封じてしまう。
少しばかり不満そうに眉根をよせるコーネリアへ、シャノンはキャディボックスの内の二種類の茶葉を示した。
「ネリー、今日のメインのお茶菓子は、アプリコットタルトです。お茶はダージリンとアッサムと用意しました。ネリーだったら、どちらを選びます?」
「……ダージリン。果物のタルトなら、たぶん、ダージリンの方がいいとおもう」
「そうだね。ダージリンなら香りもあうし、アッサムだと少しくせがあるから、アプリコットとは相性が悪いんじゃないかな」
かたわらからトリストラムが口をはさむと、少女は少しほっとしたように表情をやわらげた。
「では、ダージリンで」
シャノンも手際よく茶器を手にとり、幼い主人に代わって給仕の用意をすませてゆく。
あたためたティーポットに、丁寧に量ったダージリンの茶葉を。今日はコーネリアに茶葉を選ばせたためさすがに沸きたてのものは使えないが、湯を注ぐ。
その間、アディンセルの血筋のふたりは、テーブルに並んだお茶菓子を前にして言葉を交わしていた。
「トリスは、紅茶が好きなの? いつも、お茶会に参加したがるけれど」
「それなりに。この国に紅茶が無かった頃から、一応、亡霊でいるしね」
「紅茶が……無かった頃?」
「案外と最近なんだよ、紅茶のひろまりは。それ以前にあったのは……そう、女王陛下よりももっと前にいた王の、妃が好んで、東洋趣味の茶を嗜んでいたかな」
ふうん。とコーネリアがまたたいたところで、どうやら準備も整ったらしい。シャノンが紅茶の用意を終えて給仕をはじめる。
「でもお茶会は紅茶よりも、会話の方が好きかな。やはり、紅茶は香りを楽しむか、あるいはティーカップごしに温度に触れるだけで、飲めはしないし」
「……そうなの?」
「それはそうだよ。たとえ――誰かに触れることができたとしたって。こんな死んでいる、実体もない身だしね。それにいままで子供部屋の外に出て、誰かに気づいてもらえたためしはないし。かといって子供部屋でも、基本的に子供にしか気付いてもらえないし。子供は数年で子供部屋から出ていくから。ここのところ何十年も、ある程度の年齢の人間と会話できる機会なんてなくて。人との交流は貴重だ」
「……子供部屋に始終こもっているの、そういう理由だったんですか」
おもわずというように、トリストラムとコーネリアの会話の間で、ぽつりとシャノンが呟いた。無意識だったようで、主人の会話にわりこんでいた自分に驚きながら、すぐに失礼しました。と続ける。
「べつに、いいのに。どうせトリスはもうとうに死んでいるんだし、シャノンは私の乳母代わりでしょう、いま。すこしくらい、一緒にお喋りしたっていいわ」
「だそうだよ。俺もその方が、嬉しい。さきほども言ったけれど、同年代との会話の機会は貴重なんだよ」
どこか、いたましさすらにじむような、寂しげな声音で言いながら、トリストラムが空いている椅子を示す。
コーネリアも同意するように軽くうなずいたので、しばしの思案ののち、シャノンはそれでは、給仕が終わったら。と、いつものようにはにかんで返事をした。
子供部屋で、お茶会(ティーパーティー)が開かれるたび。現在、子供部屋に属す唯一の使用人であるシャノンが同席することは、習慣の一つとなっていた。
実のところ、彼女は乳母代わりであるとはいえ、コーネリアの両親である当代アディンセル伯夫妻に雇われている使用人にすぎないのだし、ながく続く女王の治世下において、主人と使用人の立場の線引きは明確だ。特に子供が使用人の領域である、館の階下に関わることへの目は厳しいものである。
ナースメイドであるシャノンは主人に、あるいは主人の子供であるコーネリアに仕えて得る賃金で生活をしているのだ。いくら主家アディンセルの家筋の者であるトリストラムの、あるいはある意味では主人とも呼べるコーネリアの要望であるとはいえ、そうなんでも容れるわけにもいかない。
いかないが――同席を求められているのがお茶の時間であるのなら、多少の融通はきく。
「ほんとうに、シャノン。小さな子供以外に俺のことを気付いてもらえたのは、久しぶりなんだよ」
どこか感慨深く、トリストラムが言う。目の前に並べられていく茶器をみつめながら、あるいは給仕をすばやく終えてしまおうと手を動かしながら、シャノンはそれを聞いていた。
「弟は俺のことがみえたけれど、会話はできないみたいだったし。それ以降に大人に気づいてもらえたのは、十八年前の女家庭教師だとか、七十か八十か……どれくらい前だったかな。ええと、とにかく弟の孫の娘婿とか。あとは四十年くらい前にもひとり同年代の令嬢と会ったけれど、結局彼女、うちの一族の誰だったかとの縁談が破談になって以来、さっぱり見かけなくなったしねえ」
くるくると言葉を操りつづけるトリストラムは、本人の言のとおり、会話に飢えているらしい。
シャノンもコーネリアも、子供部屋に勤めるようになってから、あるいは物心ついた時からトリストラムを見慣れているため、下手に遮ることもせず、おとなしく聞き手にまわる。
「だから、姿も見える、言葉も交わせる、幽霊だからと怖がったり物珍しがったり、態度を変えない人間なんて、ひさかたぶりで」
「……ご苦労様。トリス、お茶が入ったみたいだし、一度いただいてからにすれば?」
ひとくぎりついたところで、コーネリアが声をかけた。
給仕をしていたシャノンが一礼してから空いている席に座すのを見、トリストラムも満足そうに口を閉ざす。
三客の陶器のティーカップと、一式揃った子供のためのお茶会のためのお茶菓子や飾りを前に、一同はゆっくりと姿勢を正し、あるいは招待主の声を待った。
「では――お茶会をはじめましょう」
そうして。幼い女主人の声で、言葉は、笑みは、もう一度はなひらく。小さなお茶会は幕あけた。
「トリストラムは、ずいぶん長いこと幽霊ですよね。確か、百年以上そのままでしたか?」
いつからだったか。シャノンは常よりトリストラムを、既に生者ではないため、主と使用人の決め事ともさほど関係もないだろうからと名前で呼ぶようになっていた。少なくとも、そのようなあいまいな記憶がある。呼ばれる幽霊の方もどうやらそれに対していまだに新鮮さか面白みか、とにかく好ましさを感じているらしく、そうだよ。と、機嫌よく返答した。
「やはり、最後の最後で伯領……というより、妖精地帯から出ようと足掻いたのがいけなかったらしくてね。心残りもないのに、名付け親殿のせいでいまも昇天できない」
「ああ……くだんの、妖精の貴婦人殿」
「そう。だけど、日ごろあれだけ疎む言葉を吐いても特に反応を示さないあたり、もうこちらに興味はないんじゃないかとも、実は思うんだけれどね」
たしかに、日ごろコーネリアの世話をするかたわら、近くを浮遊しているトリストラムからシャノンが聞くことは、妖精への不満だ。
彼女とて妖精を疎むこころは強かったから、時に共感すら帯びた返答を彼に返していた。
「そうはいっても、妖精相手にこちらのならいなんて通じないじゃない。また、執着を見せるかもしれないわよ」
「うん、まあ。そのとおりなんだけれど――でも、死んでからは小妖精も見えなくなったし、踊りにも誘われなくなったから!」
結論の見えないものの無理やりに、トリストラムはだから、ね。と安定しない言葉でしめる。なにが、だから、なのだろう。コーネリアはよくわからないながらも、曖昧にティーカップを口元へはこんだ。まったく、この幽霊はやはりどこか奇妙だ。時を経すぎたせいだろうか。
――三人がいまも、その存在を信じる妖精は、確かに彼に執着していた。己が付けた名前を持つ名づけ子に。
だからこそトリストラムは妖精地帯の外へ赴くこと叶わないまま死んだのだし、また死者となってのちも、悔いも心残りもないのに、ただ亡霊として存在している。死してなお、彼は妖精地帯から離れることかなわないらしい。
妖精。善き隣人。硝子の眸の御方。
さまざまに呼び名を持つそれを、心底より信じる人はもうわずかだ。しかし子供部屋においては、妖精とはいまなお実在のものである。
「妖精も、はやく興味を失ってくれればいいのに」
ものうげにうつむいた折、頬にかかったあかい髪をかるく耳元へ遣って、亡霊は嘆息した。
「むしろ、人間が興味をなくす方が先なのでは」
淡々と、使用人はタルトをつつき、どこか願うように言う。
「どちらでもいいわよ。それよりも、もっと、きちんと住みわけてほしいわ。妖精なんて、きまぐれに棲まう領域の境を越えてきて、人のものを奪っていくし。取り戻そうとして追ったって、境界の向こうへ逃げてそれっきりなんだから!」
交わされる言葉にいやな思い出がよみがえったのか、すこしばかり苛々と、コーネリアがちいさく叫んだ。
そう、異域から手を伸ばしてくる妖精が、このいまにおいてすら実在するのは、アディンセル家の子供部屋。けれどお茶会の席につく彼らにとってここは、言うなれば暮らす場所で、帰る場所、住まう場所。ある種の聖域なのだ。そのことを、自覚していなくても、憶えていなくても、口にはしなくても。子供部屋と、時代を越えて名前を得ず、区分だけで呼ばれ続けるこの部屋は、いまこの時において、彼らの楽園だった。
……かくして。お茶会では、そして今日も子守唄(ナーサリーライム)めいた、憂いと、願いと、憤りが語られる。
――さあ、お茶会をはじめましょう。