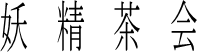
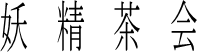
「行ってまいります、兄上」
弟がのこしていったその言葉が、もはや灯も落ちた部屋の中、いつまでも途切れず反響しているかのようだった。
アディンセル伯爵家の第二子モーリスは、この昼に妖精地帯を発った。
都のほど近くにある寄宿学校へと、とうとう彼は赴いたのだ。いまとてこうして窓辺に座すままの、トリストラムがゆけなかった、そこへ。
季節は真夏ではあるが、妖精地帯の夜は寒い。トリストラムが留まりつづける窓辺も同様で、屋内にありながらも、彼の体はとうに冷え切っていた。
大切な弟の祝われるべき門出に、年々足の自由が利かなくなっているこんな身は、ふさわしくないだろうと。またこんな身であるからこそ、きっとうまく餞(はなむけ)の笑みなど浮かべられないだろうからと。あらゆる理由をつけて、本当は見送りたくなどなかった出立を、彼はこの窓辺から見つめた。
一行の姿が見えなくなっても動く気にはなれなどしなかったから、この夜更けにあってすら、トリストラムは窓辺を――外との境を、離れられないでいる。
窓枠へと触れた手をかるく動かすと、ひやりと冴えた感覚が指先をはしる。深くかけている窓辺の椅子から、身を乗り出す事さえおっくうに感じられた。視線をかるく下へとさまよわせても、常と異なった様子もなく。見慣れた庭園の花壇で、まだつぼみを付けたばかりの夏の花々が、身を休めるようにうずくまっていた。
使用人も、今日ばかりは彼の傍を離れている。トリストラム自身がそう望んだ。
時折部屋の外をゆきかう足音、扉の前で立ち止まる気配はあるが、扉のすきまから灯りがこぼれでていないことを確かめるほどの時間がたてば、彼らは皆、廊下の先へと立ち去りゆく。まさかトリストラムが明かりも灯すことなく、昼からずっと窓辺を動かずにいるとは思ってはいないのだろう。
伯家の次代、などと。妖精地帯の跡継ぎだなどと。
そう呼ばれるごとに、失望をおぼえるようになったのはいつからだろう。
自分の名は妖精が名付けたのだということをただ戸惑っていたうちは、むしろ誇らしく思っていた。
寄宿学校へ赴くために、つまりは初めて妖精地帯の外で生きることを目指して、この土地を離れようとした時も。
そしてその結果、トリストラムの乗った馬が足を引かれて転倒し。痛みの中、聞き覚えのある人ならぬ声に、妖精に近しい者は領外へ出るなと戒められ……その実、戒めどころではなく、落馬が原因で足を悪くしたと彼が知った時も。
妖精たちへの怒りと憎悪に押しつぶされそうになりながら、トリストラムが抱いたのは、せっかくなのだから領境までは騎馬で駆けたいだなどと浮かれていた、自分の軽率さを悔い、そして妖精に絡んだ問題ばかり起こす己を恥じるという感情だった。いくら妖精地帯の領主といえど、いま伯一族が信奉するのは、この地の果ての国の国教である。ふるい時代に畏れられた、異界の住人たる妖精たちではない。
だというのに妖精絡みの厄介事を招いてばかりのトリストラムは、果たして次なる伯爵にふさわしいのか。歩けはしても、長く立つこと、走ることはもうできないほど足を悪くした身で、本当の意味で国王へ仕えること叶うのか。そう思い悩んだ。
ゆえにしばらくたっても回復の兆しを見せない足では、寄宿学校での生活は無理だろうと。医者に告げられて以来、後継であるという事実に対し、感じるようになったのは落胆ばかり。
それがしだいに、トリストラム以外の目には見えぬ妖精たちが阻むせいで、たとえば都での社交や、あるいは寄宿学校での勉強といった、貴人の子弟に求められる様々なことを為せないがゆえの苛立ちを生み。やがて、そのような彼をことさらに大切にしようとする一族におぼえたのは、困惑でしかなかった。
いくら、継承を放棄できない爵位を継ぐのがトリストラムだとしても、数十年ぶりに伯爵位を持つ人物のもとに生まれた初子であっても。それでもトリストラムは、疎まれたっておかしくない要素をこんなにも持っている。
自由の利かない足、妖精地帯から出る事が叶わないらしい身、あかるい髪は曙めいた赤色であるし、それに弟のモーリスは、幼いながらも優秀だ。さまざまな役割を慣例通りに果たせない兄よりも、ずっと見込みがある。モーリスが爵位を継げない次男であることを惜しむ声は、日頃から多かった。
だというのになぜ、厭んじないのか。憎まないのか。いたわる言葉すら、優しい笑みすら向けてくるのか。不思議に思い続けるうち、疑問は簡単に失意に転じた。
彼らは皆、伯爵家の跡継ぎではなく、一族の若者を……いや、子供を可愛がっているにすぎないのだ。
「おまえは大事な、後継なのだから」
そう、言い聞かせておきながら――彼らはトリストラムを、近い将来に伯爵家を守り負う者と見ていないことはたやすくうかがえた。矛盾しているのだ。貴人としての義務や心得を教え込むかたわら、憐れな身の上であるからと甘やかす。
あまりに滑稽だと、ここのところはよく思う。
長老と扱われる老いた大伯父、都を本拠とする従祖母一家、さまざまな功績を持つ叔父たち、歳の離れた母方の従姉たち。あるいは、代々アディンセル家に使える古参の使用人や領民。
「あなたは大切な、次代なのですから」
そううそぶいておきながら、彼らにとってトリストラムは、それはそれは可愛そうな、足の不自由という翳りゆえに未来に不安を持つ十三歳の子供でしかない。
まるで青年に成長してゆく彼の時を止めるかのように、いたわりという名前で、館の内に籠め、子供部屋(ナーサリー)めいた檻に愛情をもってして鍵をかける。
トリストラム・アディンセルは、寄宿舎に赴けずとも、足に不自由を抱えようと、国王陛下への拝謁を望めずとも――とうてい子供のままではいられないというのに。
彼らが次なる当主と呼ぶ以上は、十九の青年として立たなければならないというのに。
そう教え継ぐのは、ほかならぬ親族たちだというのに!
すうと、冴えた空気を吸い込んで、反射的に声にしようとして、やめる。
いらだっても、どうせ届くことはない。何年もの間、幾人もの者に、さんざんに心中を訴え続けても、それらが実ることはなかった。
もがくように一人、なせることをこなそうと足掻いてみても、実を結ぶことはなかった。一度は得た、あるいは掴みかけたいくつもの成果は「無理をしては、体に障る」そのような一言といたわりの手によって、抱え続けた腕の中からたやすく取り上げられてばかり。
かるく嘆息すると、トリストラムはゆっくりと立ち上がり、壁に手をついて窓から外を見下ろした。
どうすべきかは、薄々、察している。どうあれと望まれているかも。ながく、目をそらしてきたけれど。しっている。
「学んでおくれよ、俺の分まで」
遠く、丘陵のかなたを見据えて口にした声は、あまりに小さかった。
やはりトリストラムとは違い、モーリスは無事に妖精地帯を出ることができたようだ。この時刻になっても何の報せもないということから、そう判断するのはたやすかった。
ならばアディンセル家の次男は、故郷から巣立っていったのだろう。飛び立てなかった長男に代わり、人脈を築き、世情を学び、伝統を受け継ぐために。
長男に名前を、次男に役目を。それぞれ継がせれば、なるほど、不利益はない。爵位を継げない優秀なモーリスを、いずれ称号を継いだトリストラムの補佐という名目で家に残せば、伯領も安泰である。
「兄上、お体に気をつけてください。休暇で帰ってきたら、また兄上と、たくさん本が読みたいです」
トリストラムが窓辺から見送るよりも以前。最後に挨拶に来たモーリスは、そんなことも言っていた。
それにトリストラムがどう返したか、あまりよくおぼえてはいない。
うけとめたくなどなかった未来に向け、緩慢だった時間がきしんだ音をたてるように動きはじめたらしいとの自覚の方が、弟の言葉よりもなお大きな衝撃だった。
……遠い都へ赴いた弟は、きっと多くを得て帰ってくるだろう。トリストラムが持つはずだったものも、その腕には抱えられているはずだ。
わずかに口惜しさをおぼえ、トリストラムは反射的に、どこまでも続く夜空を見上げた。月は中天に程近い。ということは、時刻はそろそろ真夜中であるらしい。もやの向こうの月は真円で、満月の冷めた光はかすみかけている。
――そこで、はたと気づいた。
「そっか」
俺は、くやしいのか。
こぼれ落ちたひとりごとは、くらい部屋の中、やけに印象深く彼の耳に届く。
そうだ。口惜しいのだ。
名実ともに伯家を継ぐ者と、見られてはいないこと。
足の自由を失ったこと。たとえるならばあの日、妖精地帯から羽ばたけなかったこと。
いまこのような現状に甘んじ、ほんとうは選びたくなんかない未来への道を、進んでいるだろうこと。
失望し、恥じ、憎悪し、あるいは苛立ったことならいくらでもあった。けれども自分が一連の転落に口惜しさをおぼえていると、自覚したのはもしかしたら、初めてかもしれない。
咄嗟に意識してみれば、あとはもう、めくるめくように心が動いた。
はっとして、窓の硝子に寄り添うかのように身を乗り出し、内と外の境界ぎりぎりにまで手を触れる。地平の彼方へ視線を凝らしながら、もっと遠くを、その先にある領外の世界を見たいと、己の内ではやり湧き立つ、強烈な感情を知った。
「行きたい」
あの丘の向こうへ。ずっと向こうへ。
トリストラムとて、いきたかった。都へ、領外へ。自分の足で、立ってみたかった。いや、いまとて、いきたいのだ。人間が妖精と馴れ合わずに、生を営み続ける場所へと触れるようにして。
きっと、あこがれ続けていたそこは……しかして、あまりに遠く。
――そうやって、わたしたちをまた。おいていこうとするの――
ひさかたぶりに。音ならぬ声に、たかく、耳元で叫ばれた気がした。ぞっとするような不快感が全身をかけぬける。怯えのまま本能に任せ、トリストラムは体ごとうしろを振り向き。誰の姿もない、見慣れた自室を視界におさめると同時に、背を切り裂かれる傷みが襲った。
身がかしぎ、割れた窓の硝子が頬の横をすり抜け跳ねる。欠片がきらめいて空へ跳ね上がる――いや、あまりに強すぎる力で窓辺から押されたトリストラムが、上体からおちてゆく。
いたい。
声すら出せずに、均衡を崩して、動かない足が窓枠へ打ち付けられるのを感じていた。冴えた空気が身を切る。風がひゅうと、嘆くかのように鳴く。
いやだ。
落下の浮遊感は、不快なものだった。心だけ、どこかに置いてきてしまったかのような錯覚に囚われながら、もがくように腕を伸ばしても、なにもつかめやしない。そこでもう、悟ってしまった。終わりなのだと。
いきたい。いきたかった。
そう。生きたかった。ただの、妖精との縁なんて持たない、人間として。行きたかった。仰ぎ見るがゆえに、もう遙かに遠い、世界へ。
声もなくみひらいた、トリストラムのはしばみ色の目に。あまりにうつくしく映ったのは、かすみがかった夜のふかく、なめらかな天蓋と、そこに散らばる硝子片めいた輝きだった。
実際、散じるのは窓硝子の破片だったのかもしれない。けれどその一瞬、彼はそれを星としてみとめた。けぶるような雲の間から、みちあふれるようにして。最期にかるくまばたいた一瞬の隙間で、目蓋を刺したきらめきは、あまりに聖(きよ)く、まばゆいもので。
ふたたび眸をひらいたその時にとうとう襲いきた、身を裂き砕くような衝撃で、そして一度、彼の記憶は終わる。
強烈な喪失感と絶望と、いたみと、それから自覚したばかりの憧憬。それから、誰のものであるか――どこから聞こえたかもわからぬというのに、その夜すべての領民が耳にした、甲高い、女の悲鳴。
それらすべて、悲しみの子と。妖精に名付けられた青年が、最期の瞬間に得たものだった。
トリストラム・アディンセル。享年を十九。死因は事故による転落死。
それは夏の盛りの、ある真夜中の出来事だった。
かくして、妖精地帯にて物語られる――最後の妖精譚は幕あける。