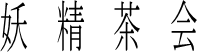
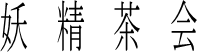
コーネリアはときおり、朝のまだ早い時間に目を覚ましてしまうことがある。白いシーツの感触、窓にきっちりとかかったカーテンの、そのわずかな隙間からにじむ、昇りかけの陽光。そんなほのかなあたたかさ触れて、かるくみじろぎをしながら、もう感じられなくなった、遠いぬくもりを思い起こすのだ。
今日もどうやらそんな風に、まだ起床の時刻よりは早い時分に目覚めてしまったらしい。まどろみめいてぼやけた意識で、彼女は枕に頬を押し付けたまま、ゆっくりと瞬いた。視界に映るのは、変わらずにおだやかな、アディンセル家の子供部屋(ナーサリー)だ。生まれたときからずっとずっと、コーネリア達が生きてきた場所。
かなしいからか、いとしいからか。どちらともつかない感情が、澄んでゆく思考に浮かび上がる。いつものようにあわく笑んで、泣きたくなるのをこらえると、コーネリアは目をこすりながら身を起こした。
幼いながらも、少女と。そう呼べる年齢になってきた彼女が、ひとりで眠り、ひとりで目覚めるようになって、もうどれくらいになるだろう。
もちろん心細い夜は、シャノンが寝かしつけてくれるし、トリストラムが見守っていてくれる。朝になれば優しい手と、朗らかな声が起こしてくれる。でも、となりあって、手を繋いで、一緒に夢へと落ちていくひとは、コーネリアの傍らから、姿を消してひさしかった。
毛布をはねのけ、ベッドからひとり、素足で床へと降り立つ。コーネリアは「シャノン、どこ」と、子供部屋に控えているはずの、使用人の少女を呼んだ。
「ネリー? もう、起きたんですか」
すこしばかりの後に、少しだけ焦って部屋の角向こうから姿を見せたシャノンは、どこか見慣れない装いだった。使用人らしい日常着である、シンプルなグレーのドレスの上には、まだエプロンもしていない。いつもは結いまとめ、シニヨンにして上げている金髪も、いまは背に流れている。彼女が起床してからも、まだ時間がたっていないのだろう。
「目が、覚めちゃったの。おはよう……トリスお兄さまは?」
こちらへと急ぎ来る彼女へ、少女はならい通りに挨拶をする。シャノンも「おはようございます」と、少しかがんで視線を合わせて、コーネリアへ返してきた。
「トリスは、いませんよ。いつも、朝方のこの時間は」
「どこかに行っているの? 」
「……さあ。夜明ける前にはもう、姿を消していますから」
そう続けられた言葉に、令嬢が一度だけまたたくと、困ったように、シャノンは口元に笑みを浮かべる。
「大丈夫、ネリーがいつも起きている時間には、帰ってきているはずですから。……さ、身支度をしましょう」
そして屈めていた身を起こすと、まだしっかりとは目覚めきっていないコーネリアをの髪を、整えるように一度だけなでる。それから、ふたつの、隣り合った小さなベッド。そのほど近くに設えられた小さなクローゼットのうち片方から、シャノンは衣類をとりだすべく手を伸ばした。
……いま、アディンセル家の子供部屋(ナーサリー)に住まう子供は、コーネリアたったひとりだけだ。それでも、この部屋には確かに、コーネリアたちが生まれた六年前、ちょうどシャノンが雇い入れられた頃から、ふたり分の家具と、玩具と、生活のための品々がところ狭しと並んでいる。
クローゼットからハイ・ウェストのワンピースを選び出すと、シャノンはいつも以上にコーネリアを手早く着替えさせてしまう。いつまでも令嬢を寝間着でいさせるわけにはいかないし、同時にシャノン自身、まだ背に流したままの金髪を、はやくまとめ上げてしまわないといけない。
それでも常ならない事は、なにかと重なるようで。
「ネリー、背が伸びましたね」
おとなしく、着替えさせられていたコーネリアの支度がひととおり整ったところで、シャノンは少女の足元に気づいて言った。
コーネリアが見下ろしてみれば、たっぷりとしたひだのスカートから、少しばかり足首が出てしまっている。以前にこの服を着た時は、そんな事もなかったのに。
「背が伸びた、の?」
「ええ。成長したんですよ。もうこの服は、替えなければ」
背が伸びたからか、たしかに袖もきつくなっている。そうだ。シャノンが言うように……コーネリアは、成長したのだろう。
ならばこの服ももしかるべき処分をし、その分新しい物をあつらえなければ。そうでなくても良家の令嬢が、あきらかに小さくなった服を着ているなど、きっとお父さまもお母さまも、顔をしかめるはずだ。でも。
「……いや」
くしゃりと、コーネリアの顔が歪む。鏡の前でウェストの高い位置に仕上げのリボンを結ぶため、幼い彼女の後ろに立っていたシャノンも、その変化に気づいた。
「ネリー」
「いやよ。おそろい、だもの」
めずらしくかんしゃくめいて、コーネリアは声をはりあげる。
いやだいやだと、駄々をこねる事など普段はめったにしない彼女のそんなさまに、シャノンは少しばかり戸惑った。
「でもネリー。あなたが大きくなってゆくごとに、もっとずっと、服は小さくなってしまいます」
するとコーネリアは跳ねるように振り返って、そんな従者のスカートを両手でつかむ。普段の令嬢然とした、年不相応な様子らしからず、そして泣きわめく寸前のような面持ちで、でも、とすがりついた。
「いやよ! だって、ロディは大人になれないのに――私だけ大きくなんて、ならないわ!」
「ネリー……」
それは、唐突すぎる変貌だった。子供は常々、彼らなりの流儀で動くものであるけれども。
しかしながら、いやよ、と。そのままシャノンのスカートに顔をうずめてぐずるコーネリアの言い分も……わかりはするのだ。
確かに、いましがた着せたばかりのグリーナウェイ・ドレスは、コーネリアたちが六歳を数えた頃よりも少し前に、姉弟揃ってあつらえたもの。男女の差もまだ見えぬほど姿かたちもそっくりな双子に、アディンセル家の夫妻が喜びとともに贈った衣服を、幼子たちは「おそろい」と呼び、ずいぶんと気にいっていた。
ロディ。ロドニー。ロドニー・アディンセル。
コーネリアの双子の片割れ。アディンセル伯家の若夫妻の長男で、やがてはアディンセルの名を継ぐはずの子供。それでも、いまこの子供部屋にはいない子供。子供部屋で生きるコーネリアの隣から、二人を世話していたシャノンの手から、家筋の子供たちを見守ってきたトリストラムの庇護下から……幼くして引き離されてしまった、少年。
「ロディと、一緒じゃなくなっちゃうじゃない」
コーネリアは、双子の弟が彼女の隣から失われて以来、執拗に思い出に縋り、ロドニーが関わったもの、すべてを手放したがらずにいる。時折は、いまのように唐突なかんしゃくすら起こすほどに。常が驚くほどに大人びている彼女だ。その行動は子供らしいとは言えるものであるが、こだわりようはしばしば目を瞠るほどである。誰も使わないというのに、片付けられる事の無い鉛の兵隊。となりあったベッドの片方にはいつも覆いがかかっているのに、玩具や家具が雑然と詰め込まれている子供部屋(ナーサリー)から、取り払われる気配もない。
「一緒じゃなくなったら、きっと、忘れちゃうわ。そんなのだめよ。忘れたらもう会えなくなるって、トリスお兄さまだって言っていた。妖精なんかにさらわれたせいで、もう会えないなんて、いや!」
それもまた、コーネリアがよく語る事だった。怒りも、嘆きも、さみしさも入りまじった子供の声は、いたましい。
シャノンは感情の高ぶりからか、とうとう泣き出してしまったコーネリアの頭をなで、抱きしめた。彼女にとっても、あの冬の夜の窓辺で、妖精の手によりうしなわれていった、ちいさな子供は大切なものだった。己の死後に繋がれていった血筋を百年以上愛してきたトリストラムにとっては、いうまでもない。
「泣かないで。目が赤くなりますよ……服は新しいものに替えたとしても、処分はしませんから。大事に、とっておきましょう。ロドニーとだって、また会えます。絶対に、また一緒に居られます」
あやすように、抱きしめた腕を少しゆるめて視線を合わせ。シャノンはコーネリアに言葉を紡ぐ。窓辺からはもう、燦と光が差し込んできている。背に長くおろしたままだった、シャノンの金髪に陽光が透けて眩しいのか、涙にまみれた顔を上げた令嬢は、ぐずりながらも少しばかり目を細くした。ひとりぼっちになって寂しかった時に、真っ先に手を繋いでくれた彼女の声を、いつだってコーネリアは信じられる。
シャノンにとっても、きっと言葉は約束だった。大切に預かって、育てあげなければならなかった、主家の子供。そのひとりを手放してしまったシャノンが、今もこの場にいることだって、その為に他ならないなのだから。
妖精にさらわれた、アディンセル家の子供。その存在は今とてなお、あかるいはずの子供部屋(ナーサリー)に、どこか歪に翳りを落としていた。