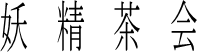
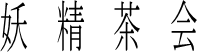
「――でもネリーは? おいてゆくのですか?」
「それしかないだろ。あの子を、あそこまでは連れて行けない。戻れなく、なる」
「……わかりました。うかがいましょう。少し待ってください、トリストラム。外套をとってきます」
「いや、いらないよ。そのままでいい。ここのところ、気候は夏が続いているようだから。それに急いだ方がいい」
そしてやがて、遠くで扉が閉まる音。
夜半、ぼんやりと浮かび上がってゆく意識の片隅で、コーネリアは親しんでひさしい二人の声を聞く。ささやくように抑えられた音を耳にしながら、彼女はまどろみを享受していた。けれどもだんだんと意識は覚醒してゆくのが、あさい眠りの常である。
しばらくたってからぼんやりと少女が身を起こした頃には、もう部屋にはコーネリア以外、誰も居なくなっていた。
「……シャノン? お兄さま?」
寝起きのほうけた頭は、ゆるくしかまわってくれない。それでも先ほど話をしていたのは、そしてコーネリアをおいて出て行ったのは、間違いなくシャノンと、そしてトリストラムだろう。
かるくみじろぎをして、コーネリアは寝台からすべり降りる。寝台脇の靴に小さな足を滑り込ませるのにもたついて、長い白地の寝衣の裾がめくれる。けれど少女にはそれすら気にする余裕はなかった。いいようのない不安感からか、思考は覚めないというのに、いやおうなく動悸ははやまっていた。
どうしてだろう。ひとりきりで、おいていかれて。誰もそばに、いなくて。こんな事ははじめてのはずだった。けれどもとてつもないほどの恐怖と、孤独と、既視感が、警鐘のように彼女の心臓を締め付ける。
靴をはいて床に立った途端、たまらず、コーネリアは足をもつれさせながらも部屋の中央へとかけ、子供部屋(ナーサリー)を見渡した。シャノンの、トリスの、誰かの姿を探して。
しかしいくら視線を走らせても、子守女中も、亡霊も、とうぜんのことながら兄弟も、そこにはいない。本当にひとりきりだ。床に置かれた木馬や人形の家、壁に大きく広がる窓、いつか兄弟で、大切なものを入れようと決めた硝子戸の本棚。見慣れた子供部屋は広がれど、そこに誰かの姿はない。
自覚してしまえばあとはもう、不安しかおぼえられなかった。しばし思考が停止して、じわりと涙が浮かび続けた。
「やだ」
ぽつりと声をこぼすとともに、彼女はふらふらと歩を進める。視線の先には、子供部屋の壁に設えられた大きな扉。きっと、シャノンとトリスが出ていったに違いない、たったひとつの出入り口だ。
もしかしたら、今からでも追いつけるかもしれない。そうでなくても、扉の先はアディンセル家の廊下だ。探せば誰かいるかもしれない。歩み出せばそんな期待がふくれあがり、気付けば走り出していた。部屋の外へ赴くにふさわしいきちんとした身なりではないが、それでもいい。
立ち止まりなどせずにドアノブに手をかけ。アディンセル家のたったひとりの令嬢は、力を籠めて扉を押し開く。
そして、瞬間。
むせかえるような湿った香(か)が、コーネリアの頬をなでた。風が髪をもてあそび、草花の息吹が肌に触れる。涙でぬれた目元ですうと清(さや)さを感じた。やわい寝衣のスカートが大気をはらんであおられ、小さな靴につつまれた足はもつれるようにして地を踏み、動きを止める。
眼前に広がるのは、墳丘めいてどこまでも緩やかに折り重なる、妖精地帯独特の丘陵地形だ。けれどもそこかしこには、四季の野の花が無秩序に咲き乱れており、丘向こうの薄曇りの雲は、妙にあかるすぎる。夜の気配などどこにもなく、世界はあきらかに真昼。
寒さを感じさせない風が、陽光をさえぎるかのように渡りゆく。それだけでなく丘のはるか先には、どこまでも遠い水辺の青と、わずかに反射する光のきらめきがみてとれた。
そこにあるはずだと少女が信じていた、アディンセル家の二階の廊下は、どこにもない。先程まで彼女が身を沈めていた夜も、気配すら感じられない。扉の先に広がったうつくしい丘陵に、コーネリアは息をのみ、そしてゆっくりと、あさい呼吸を繰り返す。
「……わたし」
忘れて、いた。
おもわずあわい吐息にまぎれて、声がもれた。不可解な事態に、混乱したのではない。彼女はこの奇妙な景色を知っていた。そして今、衝撃とともに思い出したのだ。
さきほどから涙ににじみきった視界は、それでも水と草地の境界線の見えない碧と、そこに散る花々の彩(さや)かさで満たされている。けれどこれ以上踏み出す勇気はない。右手は少し高い位置のドアノブに触れたままで、いやに冷えたその感触だけが救いだった。
――コーネリアはおもいだす。大切なことを、たくさん、彼女は忘れ去っていたのだと。
現実になんて、ありえない場所。
いやに奇妙でうつくしい、風景。
いつか。コーネリア・アディンセルは、たったひとり、こんなこの世ならざる場所でひとりで泣いていた。大好きな手をふりはらって、窓辺から身を乗り出した夜を越えて、この地に放り出されたその時、そばには誰もいなかった。ほんとうに恐ろしくて仕方がなかった時の記憶は根深く、彼女の身にすら焼き付いていたのだ。そう、本当はひとりきりで寂しかったことだって、はじめてなんかじゃない。
「わたし、は。ロディを、まもれた、の」
奔流のようによみがえってくる、どこかに置き忘れてしまっていたらしい記憶は、とぎれとぎれの言葉と反していやにあざやかだ。夜の窓辺の冴えた空気も、恐怖に彩られ耳をうった彼女の声も、手を引かれて落ちてゆく浮遊感も、まさに今感じているかのようだった。
あの夜を、どうして忘れていたのだろう。子供部屋の窓辺から、かの妖精が手招いたこと。いとしい弟、ロドニーの身代わりになって、コーネリアが妖精の手をとったこと。そうしてこの他界の妖精国にかどわかされてきたこと。劇的に印象深い記憶を、少女は奇妙なまでにきれいに失っていた。……最後に見た弟の表情は、この他界に落ちてもけっして忘れ得ぬことを、確信しきってすらいたのに。
ざんと、扉の上方、はるかな空を伝って、東からの風が渡りくる。コーネリアはおもわず、涙にまみれた頬で天を仰いだ。澄みわった空気は、本来の彼女の故郷である妖精地帯には存在しない、潮の気配に満ちている。不意に風を追いかけて、壁にしつらえられているわけでもないのにたった一枚揺らぎもしないで、丘陵地帯に立ち尽くすドアの向こうへ振り返れば、果てからわずかに漂う、薔薇のあまやかな匂いが彼女にまとわりついた。
……かくて、その日。
アディンセル伯家のたったひとりの令嬢コーネリアは、今、立ちすくむこの場所が、生きる者のすむ場所ではないという事実を思いだし。
空に魚が押し籠められたかのように。彼女があまりに不自然に暮らしてきたこの場所は、妖精の国であるという現実をするどく思いしった。