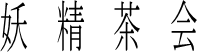
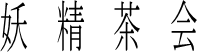
彼がその部屋で生きることなど、ほんとうは望まれてなどいなかった。
あんなことがあった場所だから、部屋をうつりましょう。あなたはたったひとりの、私たちの息子なのよ。もしも、もしも二度目があったら、お母さまたちは胸が張り裂けてしまうわ。
すっかりやつれ、涙で頬を濡らした母は、少年に何度も何度も、そう懇願した。父も懸命に、息子にせめて部屋を変えるようにと言い続けた。長子をなくしたいたみに堪えかね、たったひとり残された第二子は、ぜったいに無事に生かそうと……あの星降るような夜の記憶がいろこく残るこの部屋から、せめてひとりきりになってしまった、大切な息子を遠ざけようと。その一心で、ふたりは諭し続けたのだろうとおもう。
もちろん、このアディンセルの家うちにおいて誰もが厭う夜を、彼とて忘れたことはない。大切なひとが、死んだ夜を。彼は生涯、忘れないだろう。しかしながら、少年はかの夜の出来事を疎むからこそ、今日この日まで、この部屋を離れようとはしなかった。
いま彼のかたわらには、見守るというにはいささか過保護とみえる態で、母の侍女が控えている。あの夜以来、夫人は一人きりとなってしまった息子を手放さず、周囲のたしなめる声を振り払って、彼を手元で育てだした。結婚前から女主人の側に居たという侍女も、貴婦人のあまりの憔悴に胸をうたれたのだろう。女主人に助力するのみならず、たとえ世間一般の良識から外れたとしても、主の意に適うようこまやかな気遣いをみせた。
けれども当然のことながら、みなが彼女のように、彼ら家族に心から寄り添ったわけではなかった。
奥様はずいぶんお嘆きに。旦那様もやつれておられる。伯爵は方々へ捜索の手を伸ばしてはいるらしいが……。でも、あの高さから落ちたのでしょう? たとえ遺体がみつからないのだといったって、もうとうに死んでいるに決まっている――。
使用人が、領民が、親族が。彼ら家族へ、いたわりの言葉を告げてくる裏でそう噂していることは知っている。それでも諦められなどしなかったから、少年は心配し、諭してくる両親の声すら拒絶して、いたましい記憶の残る部屋から居を移さずに、この一年を過ごしてきた。ここから離れてしまったら、もう縁だって切れてしまうかもしれない。ここで待っていたら、きっと帰ってきてくれるかもしれない。そう恐れ、そして期待したからこそ。
けれど、それも今日で最後。
少年はくちもとを引き結びながら、生活の気配がなくなり、がらんとうつろになった部屋を見渡す。
代々、受け継がれてきた調度も。彼らのためにあつらえられた椅子や、机や。それから大切なものをしまうのだと、ふたりで決めた戸つきの本棚も。みな、この部屋に置き去りにして、彼は両親が跡取りの為にと用意した部屋へ移る。
ほんとうは離れたくなどない。人はこの部屋を、かなしい記憶ばかりに満ちているという。けれど彼にとっては、この部屋はいまでも、幸福の象徴だ。
生まれ落ちた日から今日この日まで。彼はこの部屋で生きてきた。寄り添いあったぬくもり、髪をなでる優しい手、本を読み聞かせてくれた低い声。眠れない夜には、ふるい妖精の物語を、たくさん聞かせてもらった。晴れた昼下がりには、部屋の外へは出られない亡き青年のために、花や木の葉や、小さな小石。おもいつくままに外の景色をせいいっぱい届けた。
喧嘩をして泣いた。お茶の時間に笑った。いつくしまれたしあわせ。いとおしんでもらった記憶。いつだって、守ってもらっていた。たいせつな思い出は、けれどももはや遠い。大好きなひとはあの真夏の夜に、星めぐる空にのまれて、それきりだ。
だからこそ。抱きしめつづけるそんな記憶を、けして手放すものかと。たった一夜を厭うことで、すべてを過去のものとはしないためにと。そう信じ続けているからこそ、彼はこの部屋以外の場所で生きる事を、この一年間、拒否してきた。その行為が間違っていたとはおもわない。それでも、今日でこの部屋は閉ざされる。
七歳の誕生日を目前に控え、アディンセル家の第二子は、子供部屋から巣立つのだ。
長子をなくした伯家の家督はあらためて、弟である彼が継ぐことがさだまった。
年齢からすれば、いくぶんか早いことではある。しかしいくら代々、一家の子供たちが育ってきた場所だとはいえ、人死にが出た子供部屋に、いつまでもひとり息子をとどめおくなど。かの不幸以来、ことさらに少年を大切にする両親からすれば、そのようなことは些細な問題にすぎない。
それが彼にとって、たまらなくくやしく、口惜しく、耐えたくはない理不尽だったとしても。
引き寄せられるようにふらりと、少年は不意に窓の方へ視線を遣った。出窓めいて大きなそれの向こうには、風吹きぬける妖精地帯の丘陵が、どこまでも続いている。陽光はわずかかすみ、昼下がりのおだやかな空気のゆらぎが心地よかった。
『いつか』
けれども。なくしてしまった穏やかな窓辺は、いまはもう、記憶の中にしかない。いま、この部屋に残されているのは、誰も近づかないよう、近づいても開けられぬよう、まちがっても落下せぬよう、周縁を武骨な鉄の柵で囲われて、冷たく閉ざされた窓ばかり。
『あなたがたのそばから、トリストラムがいなくなるまでは――きっと私もここにいることができると、おもいますよ』
泣きはらしたのだろう、あかい目元を隠したひとに、それならずっと、ぼくらは一緒にいられるねと。だってお兄さまはぜったいにぼくらを、すぐ隣で守ってくださるからと。そう元気づけようと、彼は、かつて無邪気にはしゃいでみせた。
だって、彼は信じていたのだ。ずっと、無邪気に信じていた。こわいものも、おそろしいものも、いやなことも。みんなぼくらの頭上で払いのけてくれるお兄さまは、ずっとずっと、そばにいてくれるのだ、と。だというのなら、彼らがのぞんだ安穏は、きっといつまでも終わらない、しあわせな物語となるはずで。
そうやってただ、愛情と平和を信じつづけていたからこその――この、結末である。
守られて、守られて、守られて。そうしてここには少年ひとりだけがとりのこされた。
かの、星空のさえわたった夜を境に、悲劇はめまぐるしく幕あけて、そして彼だけをとりのこして終わってしまった。以来、アディンセル家に訪れるのは、かなしいかなしいと降り止まぬ、ながい涙の雨ばかり。いくら月日がめぐろうとも、伯家の時間は、きっとあの星空のたもとで、止まってしまったままなのだ。いまはなきひと。自らかたむいて落ち去ってしまった、あなたの示しおいた夜は、きっといつまでも終われない。
いつのまにか伏せていた視線を、少年はぐっと、大きくあげる。
この風景を、大人になって、老いて、死ぬまで。忘れなどしないようにと、身に焼きつけておきたかった。
そのような彼の姿勢に呼応するかのように……瞬間、閉ざされていたはずの窓から風がざんと吹きいった。大きな音を立てて硝子戸が開かれるとともに、大気が室内をめぐり満つ。そばにいた侍女のスカートが、風をふくんでひろがる。少年の髪も強くなでられた。けれども風かけるなかに、白いものを見た彼は、そのようなこと気にする間もなく、反射的に窓辺へと駆けより、宙にあおられた封筒へ手を伸ばす。掴み、とる。
「ロドニー様!」
おそれと驚きをいりまじらせながら、侍女が血相を変えて彼を追った。そのまま、両の手で封筒を掴んだ少年を、うしろからひきとめるように抱きしめる。アディンセル家に住まう人々がおそれる窓辺は、いま彼の目前にあった。手段を選ぶ暇など、なかったのだ。
「窓には近寄らないと、約束でしょう……!」
頭上からふる青ざめた声を、少年が気にとめることはなかった。さあ、とうながされて背を押され、部屋の外へ導かれようとも、素直に従う。彼は手の中におさまった便りに、心を奪われきっていた。
「なんで」
きっちりと蝋で閉じられた封筒から、視線が外せない。取り落とした声に、侍女が怪訝そうに歩を止めた。
「トリスお兄さま――そこに、いるの?」
彼は咄嗟に、アディンセル家の子供部屋を、いとおしい窓辺を振り返る。自然、じわりとぼやける視界に、あいするものをおさめたかった。大切なひとがもう、そこにはいないと知っていたって。
彼の手元の封筒に視線を遣った侍女は、眉をひそめる。封蝋には、古い時代のアディンセルの紋章。差出人には、アディンセルの名前。
「ロドニー様、これは……」
声をかけると、少年は常ならずあわて、袖口で目元をこすった。そうして、開け放たれた窓辺から振り返り、いかなくちゃ。と声を震わせる。
「お父さまのところに行かなくちゃ。おじいさまでもいい。叔母さまでも! だって、トリストラムお兄さまからのお手紙なんだから!」
かたくおされた封蝋の紋章は、違(たが)うものか。いまは亡き彼のもの。
『愛するロドニー、そして、いつか愛した子供たち。アディンセルの血族たちへ』
少年はぱっと身をひるがえすと、今度は廊下へとまろびでる。そのまま行儀を気にする余裕もなく、ロドニーは手紙をたいせつに抱きしめて、父の書斎を目指し駆けた。うしろからは侍女があわてて声をあげ、後を追う。
差出人は――アディンセルの令嬢が行方をくらまし、子供部屋で人死にが出たかの夜を契機として、やがてはその姿を見せなくなった亡霊。
代々のアディンセルを見守ってきた、かつての当主の亡き兄は。トリストラム・アディンセルは。
きっといまとても、子供部屋とその住人(すみびと)を、心からいつくしんでいる。