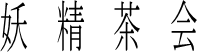
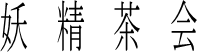
終わってしまう。
いつくしみ、いとおしまれた時間は、いつか必ず終わってしまう。絶対に。
そのことをふかく思い知らされる真夜中すぎのひととき、誰もが寝静まった夜半は、彼女にとってなによりも恐ろしいもの。ゆえにいまも、昔も。灯りが落ちてから、ベッドにもぐりこんで。それから夢を見ることもなく真夜中すぎから明けの頃まで、夜の隙間で怯えて過ごすことを、シャノンはなにより疎んじていた。
子供部屋(ナーサリー)の片隅にしつらえられた、ちいさな小部屋がシャノンの眠る場所だ。もちろん、朝になれば身支度もここで整えるし、衣服をはじめとした数少ない私物もここにしまわれている。
シャノンはコーネリアを寝かしつけ、子供部屋を整え終えると、この小部屋へ引き上げてくる。そうして、狭い小部屋の大部分を占める、簡素なベッドに腰を下ろすのだった。孤児院に居た頃のものに比べればずいぶん上等であるとはいえ、使用人に与えられるものなのだから、ベッドは狭く固い。居心地が良いとは言えなかったが、ひどく疲れ果てている時などは、そのままついつい横になって、しばし休んでから寝支度を整えることも多い。
ただし、そのように疲労が身を食(は)んでいたとしても――シャノンが正しく、眠りというものに落ちることは、決してなかった。
彼女は眠るということをよく理解できない。眠るというのは、やすらかなもののはずだ。おそれて怯えて、曖昧に過ごすものではない。そのはずだ。それでも、毛布にくるまって目蓋を閉じている間は、疑似的にまどろみを享受しているように錯覚できる。
だからその夜も、シャノンはベッドに腰を下ろすと、靴も脱がぬままうずくまるようにして横たわり、細い肩を毛布できつくくるんだ。そうしてしばらくの間、ただぼんやりと宙を見つめていた。
幾年も、幾年も。彼女はこうやって夜を越えてきた。幼い少女であった頃からずっと、変わらずに。
シャノンは妖精地帯西方の、小さな孤児院の育ちである。いまも妖精信仰が根強い土地柄であるからだろうか。かつての女子修道院の流れをくむ施設であるにもかかわらず、孤児院の住人は子供たちも、大人たちも、みな妖精をひどく畏れて暮らしていた。周辺の住人達も同様だった。だからだろう、身の半分に妖精の血が流れるとされたシャノンは、ずいぶんと厭われたし、疎まれたし、いわれのない憎しみにさらされて育った。
妖精娘。
それがシャノン・サリスの呼び名であり、蝕むようにつきまとう、妖精の取り替え子(チェンジリング)の遺児としての呪い。
彼女を産んだ母は、シャノンが育った孤児院からもほど近い場所に位置する小さな町で、妖精の取り替え子として生まれた。
きっと異変を運んでくる。なにせ彼女は、妖精が取り替えていった、妖精の子供。ならば大切にせねばならない。醜いもの、酷なもの、よからぬもの、なにごともその子に見せてはならない。妖精の手元に連れ去られていった人間の子供が、可愛がられて育つように。
昔々から、そう、うたわれるとおりに。シャノンの母は病がちの身をいたわられ、世のうつくしからぬものごとすべてから、遠ざけられて育てられた女だった。
そんな、箱入りの娘だった彼女はある年、海の向こうの系譜に連なる、若い男と出会ってしまう。飢え苦しんで故郷から逃げ出してきた一家が、妖精地帯からも遠く離れた海辺の街で産んだ末子(すえご)。そのような、元は異国の人間である男の出自ゆえに、二人は結婚を反対された。けれど手に手を取って家を飛び出し、彼女が彼の子を産むのに、長い年月はかからなかった。
商人として身を立てていた青灰色の眸の若い男のその後についてシャノンは、自分がまだ生まれもしないうちに女王陛下の膝元の街へ赴いた、ということしか知らない。妖精の取り替え子と呼ばれた女が、産後の長患いの末にとうとう妖精国へと去ってからも、彼が帰ってくることはなかったのだ。心変わりでもしたのか、事件か事故か、病にでも遭ったのか。不況にあえぐ混沌とした都において、深く蔓延っていた薄暗い阿片窟にでも転がり落ちたのか。もはや父親だという人の行方を、娘が知ることはとうとうなかった。
母は死に、父はおらず。どうやら幾人かいたらしい親類縁者も、シャノンが生まれる少し前に訪った不況のあおりをうけてか、たやすく離散してひさしく。母が今際に身を寄せた孤児院で、そんな境遇の嬰児(みどりご)は、少女になるまでを過ごした。望まれぬ異変を運び来た、異質な妖精の取り替え子の遺児、そのいびつな不吉さの象徴である、妖精娘と呼ばれながら。
孤児院で生きた日々の記憶は、真夜中の青褪めた月の光のようにおぼろげだ。土地深くに根付いた妖精信仰ゆえに、似通った境遇であるはずの子供達からも遠巻きに距離を隔てられ続けた生活を、もう、こまかに思いだすこともない。けれども傷つくこともできなかった記憶と、かつてひとりきりで生きていた小さなシャノン・サリスへ憶えるいたみだけは、まだあざやかに彼女を蝕んでいた。
ゆっくりと、シャノンは青灰色の目を歪める。ちいさく、吐息にそえるように、彼女は薄い毛布の隙間へ呟きを落とす。
「どれも、ぜんぶ」
とうに終わったはずなのに、と。そう続けかけた言葉は、けれども最後までささやかれることはなかった。
かるく、小部屋の扉が叩かれたのだ。
「……トリストラム?」
他に思い当たる人もなく、みじろぎをしてベッドの上で身を起こすと、音もなく扉があいた。呼んだ名のとおりに、あかい髪の亡霊は、後ろ手でそっとドアノブをもどしてから、静かにシャノンのかたわらまで歩み寄る。当世風の外套を纏った彼は、今しがたくぐってきた扉の向こうの子供部屋で眠る、コーネリアに配慮してだろうか。身をかがめて、近い位置で彼女の名を呼んだ。
「夜分にごめんね。でも、今じゃないと駄目なんだ。ネリーに悟られたらいけない」
低く抑えられた声に、シャノンが反射的に顔を上げると、トリストラムは縋るように覗き込んだ。先程まで彼女がくるまっていた毛布をはらうようにして、彼はシャノンの腕に指をのばす。
「来て、シャノン」
怪訝に思いながらも、急くようなトリストラムに腕を引かれるがまま、シャノンは再び床に立った。トリストラムはそのまま扉をあけて、急ぎ足で彼女の手を引いて歩いてゆく。真夜中の子供部屋の灯りは落とされており、ちらりと子供用のベッドに視線を遣れば、コーネリアは穏やかに眠っていた。
「何があったんですか」
尋ねると、子供部屋の幽霊は振り返らずに早口で答える。
「妖精国が削られている」
「それは」
「妖精国の……それも川岸近くの領土が、また減りだしたらしい。ともかく確かめて、ことの次第を把握しないと。来て、シャノン。もしも川にまで異変が訪っていたとしたら、妖精国に君臨する者だって変わるかもしれない――君が妖精夫人(レディ・フェアリー)と交わした契約も、どうにかできるかもしれない」
トリストラムのはしばみ色の眸に浮かぶ、口惜しさとわずかな期待を意識的に無視して、シャノンは一瞬だけ躊躇ってから、尋ねる。
「――でもネリーは? おいてゆくのですか?」
「それしかないだろ。あの子を、あそこまでは連れて行けない。戻れなく、なる」
いつだって、子供のそばに。そうして病からも、怪我からも、貴族の子にふさわしからぬ所作や価値観からも、遠ざけて守り育てる。そんなナースメイドとしての職に背けと暗に言うトリストラムへの声に、少しばかり非難の色が混ざったのは仕方のないことだろう。むしろ、いままで散々このトリストラムに手を引かれて、貴族の子に最も近しい使用人としての職に背いてきた身であるからこそ、躊躇いは強かった。
そもそも、いまのこの乳母(ナニー)もいない子供部屋に、コーネリアをひとり置いたまま、大人が誰も……死せる身とはいえ青年であるトリストラムどころか、ナースメイドのシャノンまでいなくなるなんて。とんでもないことだ。
しかし彼女はそのような憂慮をわずかな時間憶えるも、結果的には覚悟を決めた。トリストラムが「妖精国に君臨する者だって変わるかもしれない」「シャノンと妖精夫人の契約もどうにかできるかもしれない」などと言っているのならば――それはつまり、停滞しきってひさしい妖精国において、なにか変革が起ころうとしているのかもしれない。もしそうなのだとしたら、コーネリアという少女を守りたいを思う以上、この機を逃してはならなかった。
「……わかりました。うかがいましょう。少し待ってください、トリストラム。外套をとってきます」
せめてなにか羽織った方がよい。どこへゆくにしても、夜道の風は冷えているだろう。それに子供部屋の外の無秩序にうつろい乱れる季節が今なんであるかを、ずっと子供部屋から離れずにいたシャノンは知らないのだから、備えるだけ備えた方がよいに違いない。
ところが、トリストラムはそんなシャノンを制すように、自分が羽織っていた外套を脱いで、シャノンに慌ただしく着せかけた。そのままで、ふたたび言葉を連ねつつ、彼女の肩を抱いて自分の方へ引き寄せると、子供部屋の外へ急ぎ歩をはやめる。
「いや、いらないよ。そのままでいい。ここのところ、気候は夏が続いているようだから。それに急いだ方がいい」
そして、扉をひらいて。
トリストラムに先導され、シャノンはその夜、この子供部屋にやって来てから初めて、仕え守るべきコーネリアのそばを離れた。