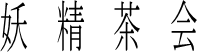
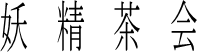
トリストラムは、約束を抱いている。
だから、この夜の明ける時間。彼は子供部屋(ナーサリー)から姿を消し、人の世のどこにあるともしれぬ――もしかしたら現(うつつ)のどこにもないのかもしれぬ、薔薇庭園の女主人のもとを訪ねる。
そして朝焼けの陽をうける花園の中心にて、既に人の身とは言えぬ者同士、ふたり、茶会の席につくのだ。
薔薇の花だけが咲き乱れる庭園は、いつでも穏やかな風が吹いている。澄んだ大気の揺らぎは、花づいた生垣と、それらを囲む石造りの低い塀の向こう側に広がる、なだらかな丘陵地帯の果てより訪い来るもの。
そんな園の薔薇は女主人の為だけに咲き、香りもまた彼女の身にだけまといつく。いくら客人がその場に長居しようとも、薔薇庭園から一歩でも出れば、その残り香さえ楽しむことはできない。考えてみれば不可思議なことではあったが――人のならいなど通用しないのだろうこの場所で、それはなぜ、だなどと考える者はいなかった。
「トリストラム」
薔薇庭園の女主人は、手元に置いた甘い色の茶器を、その細い手で包みながら、客人の名を優しく呼んだ。
「お嬢さんはお元気かしら」
「……それはどちらの? 妖精夫人(レディ・フェアリー)」
赤い髪の亡霊は、うつくしい淑女の問いかけに、少しばかり眉をひそめる。不愉快さや、苛立ちは隠さない。
妖精夫人と呼ばれた女は、まだ若い。二十代の半ばほどだろう。しかし真白い肌も、淡い金の髪も艶やかで、ほころぶように笑まうさまは、さながら夢見がちな若い娘のようだった。それでも、人が彼女を乙女と見紛うことは、決してないだろう。華やかながらも翳りのみえる表情や、落ちついてやわらかな声音の無邪気な印象を打ち消すほどに、女が纏うのは、母性。子を慈しむ母だけがそそぐその視線を、妖精夫人はもっていた。
「あなたの、お嬢さんよ。トリストラム。あなたの大事なお嬢さんは、お元気?」
けれども、そう尋ねてくる彼女の身に着けた服飾は、百年以上も時代遅れ。夜空の色をしたドレスも、この女王治世下の現在では、肖像画の中以外では、見かけなくなった装いだ。
「変わりは、ないですよ」
「そう。それでは変わりなく、彼女は子供部屋で過ごしているのね」
「ええ。俺の大切なひとは、いつだって子供部屋の住人でいたがりますから。なにせ、そうでなければ奪われてばかりだ」
かるく皮肉交じりに言うと、妖精夫人は曖昧に微笑む。
目の前のテーブルには、陶器のティーセットがひとそろい。カップにはなみなみと紅茶が注がれており、添えられた菓子は色とりどりの花弁の砂糖漬け。トリストラムはひとくち、ふたくちとティーカップの中身を飲み干すと、もう一度「妖精夫人」と彼女を呼んだ。
「此度も、言伝(ことづて)をお願いできますか」
言葉を選んで問いかけると、女はそうね、とまっすぐにトリストラムを見た。
「よろしいわ。言葉を差し出すのはあなた。宛てるのは、だあれ?」
「境界を越えて、アディンセル家の、子供部屋へ。子供部屋の小さな主人へ」
「うけたまわりましょう。約束だものね」
そう朗らかに言う妖精夫人に、トリストラムは不服を憶えながら少しばかり、息を詰まらせる。ゆっくりと呼吸の動作を取り戻すも、それではこれを、と。言いながら、ジャケットの内側から手紙を取りだそうとして無意味に内布をこする指先には、明らかな焦りと、それから不満がにじんでいた。約束。約束だなどと、彼女がこの決まりごとを、「約束」と語ることはどうにも不満だった。彼と、彼が大切にする少女にとってのすべての不幸、その元凶は、まぎれもなくこの妖精女だというのに。
「これをお願いします、夫人(レディ)。ロドニーの手元まで」
「ええ。確かに。約束のとおりに、他界へ告げ知らせましょうね」
けれど、彼女が述べることは、そのとおり、正しい。トリストラムと、妖精夫人の契約ごとの中身は、どこまでも単純で、簡単なのだから。
ひとつ、トリストラムは約束を抱いている。ふたつ、トリストラムは約定を抱えている。
ふたつ持つ約定の契約条項は絶対だ。トリストラムにも、妖精夫人にも、もはや変える事すらできないほど、古くから繋がる鉄の掟。そのひとつめは、彼が望むというならば妖精夫人は現と異界の境界線すらも越え、ふるい掟から外れぬ範囲という条件付きで、その望みをかなえるということ。生涯たった三度だけ使うことを許されたそれは、いわば善き妖精の名づけ親としての妖精夫人から、妖精に愛された名づけ子としてのトリストラムへの贈り物と。かつてはそう呼ばれもした、宝物めいた約束であるはずだったもの。
ただしく生きていた頃はもてあまし、亡霊となって以来もながく不要の産物だったその権利を、トリストラムは半年前に、とうとう行使することを決めた。以来、必ず朝が訪うごとに妖精夫人の薔薇庭園に参じては、彼女へ問いを投げかけている。三つの「贈り物」を、どう使うか。どのように使えば、たったひとつのさいわいを取り戻せるのか。その糸口を探そうと。それは今日も、昨日も、一昨日も、その前も続いたことだ。望む道筋を見つけられない限りは、明日も、明後日も、その次も、もしかしたらこの先ずっと、永遠に続くかもしれないこと。
「……トリストラム。あなたはまだ、夜空を越えたがるままなのね」
女は唄うように言いながら、受け取った手紙をくるりともてあそぶようにして、丘陵を吹き渡る風にのせて手放した。
風は途切れずに丘を走り、やがて海へ至ると聞く。朝焼けの中、あっというまに見えなくなった手紙の消えた方向を、そのずっと向こうにあるのだろう海の最果てを越えるようにと、トリストラムは祈るように一瞥する。
こうして、手紙を託しては他界の子供へ届けること。最初の贈り物を、そのように使うことを妖精夫人に告げたのは、つい先日の事だった。はじめて願った。妖精相手に、はじめて願いを告げた。
すべては、気が遠くなりそうなほどの可能性の中から、たったひとつを選び取りたいからこそ。ゆえにトリストラムは日毎、いわば道標の手がかりである妖精夫人を訪ね続けている。
「越えられたらと、願いますよ。いつまでだって」
それでも、こうして何度茶会の席を囲もうとも、どうにも彼は、この名付け親をとうてい好めはしなかった。
「今日はもう、お暇します。妖精夫人」
ならば、用向きも片付いた以上、トリストラムはこの園を立ち去り、アディンセル家の子供部屋へ、いっときでも早く帰るべきだった。それがふたつめの約定を妖精夫人とトリストラムが交わすにあたり、彼が望んだことなのだから。叶う限りを、トリストラムは、子供部屋に住まうひとの隣にいることを選んだ。
「あら……いつまでも居てくれても、わたくしはよいのよ?」
ゆうるりと笑まう妖精夫人に目礼だけすると、亡霊は椅子を引いて席を立つ。不快をあらわにしても傷つきなどせず、人間らしい感情の動きを見せない、もはや人間として生きてはいない女は、いつだってこうして微笑んでは、甘い言葉ばかりを吐いてくる。
「シャノンとネリーが、きっと帰りを待っていますから。お邪魔しました」
「そう? では、さようならね。トリストラム。また明日も来るのでしたら、歓迎しますよ」
立ち去り際に目礼を返し、すぐさま背を向け歩き出すと、トリストラムは少しばかり早い歩で、茶会の席から遠ざかる。草地の上に散った薔薇の花弁を、ためらうことなく踏みゆけば、後ろからもう一度、ほそく言葉が言い添えられた。
「いつか――あなたの大切なお嬢さんも、連れておいでなさい。きちんと、手を繋いでね」
常よりわずかにひくい声で告げられた、名づけ親の言に。
「いいえ。連れては来ません。手だってもう、きっと昔のように繋げはしませんから」
振り向きもせずに冷たく返すと、トリストラムは薔薇庭園の外へと続く、いとふるき紋様の刻み飾られた、鉄格子めいて冷たい石の門をくぐった。