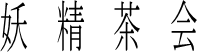
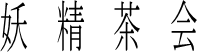
もしも陽光にくゆる翅の欠片を垣間見たのなら、日が沈むまえに若木の枝を折って、白いミルクの器に飾り、宵の境へ供しなさい。硝子の眸(ひとみ)の妖精が、眠るあなたの枕辺へ、訪うことのないように。
祖母が孫に伝える、語り古された御伽噺の文句は、地の果てに座す王国において、誰もが知っている子守唄(ナーサリーライム)だ。
特に、妖精国への道筋がいくつも隠されているという、丘陵地帯の村々では珍しくもないかたりごと。
しかしながら、都においてはそのような物語は少しずつ途絶えていたし、廃れかけの言葉たちを、人々は以前ほどつよくは信じなくなっている。
それでもいまなお根強く、数々の妖精譚を日々の営みにとなりあうものとしておそれる、御伽噺めいた土地はのこっていた。
いわく、妖精地帯と人は呼ぶ。
大陸とは海によって隔てられた島国の、いくぶんか都から離れたその西の地に、家人の皆が皆、一様に妖精の存在を信じる、アディンセルの家筋は根付いていた。
なんでもアディンセル伯家の次代殿は、妖精の名づけ子であるのだという。そのためか、伯領の住人達も多くが御伽噺を信じきっており、嘘か真か、妖精を見たと、言葉を交わしたという領民の声は、日ごろから領のあちこちでささやかれていた。
そのような話題においてまず噂される筆頭であるのは、やはり件の貴人殿だろう。
善き妖精の貴婦人に与えられた名を、トリストラム・アディンセル。時に翅持ちの妖精を伝令に飛ばし、午後には小妖精たちに粉砂糖をふるまい、真夜中には墳丘へと幽霊馬を駆り、妖精の輪に参じて踊りあかすという、いわば妖精まがい。うら若き彼の人はそのうちに、奥方すら人ならざる御方を娶るのではないかというのが、妖精地帯とあだなされる伯領の住人達の間でのもっぱらの噂だった。
だからこそ伯家の第二子である、モーリス・アディンセルは時に戸惑うのだ。赤毛との言葉で呼ぶにはいささかあざやかすぎる髪を持つ兄、トリストラムは、確かに妖精の名づけ子であると、彼は父より聞いている。称号の継承の後は、妖精伯などと呼ばれるようになるやもしれぬなとすら、当代伯はわらっていった。
しかしそういった噂や、言葉や、評価の当人であるトリストラムは、かようなこと認めたくはないらしく。よって、なかなかに自由のきかない病がちな兄を見舞い、妖精を憎む彼の姿を窓辺の光のなかに垣間見る日々は、モーリスがナーサリーを出た、ここ三年ほどずっと続いていた。
「だいたい、どうしてこうもひどい名前をつけるんだろうね。善きものと謳われている以上、多少は言葉を選んだ方が賢いのではないかな」
今日は調子がよいのだろうか。西の廊下に沿った三つ目の扉をたたいたモーリスを、窓辺の椅子で出迎えたトリストラムは、一冊の書物を手にしていた。なんという本なの、兄上。そう無邪気にたずねるモーリスに、母上がお貸しくださった、円卓の、竪琴弾きの騎士の話だよと。少年は淡々とかえして本を弟の手にのせる。彼はそうしてあきれたように、善きもの、つまりは名付け親の妖精に対しおもうところを、今日も呟いたのだった。
「呪いでも祝いでもいいけれど、人間に関わりたがる以上はうまくとりつくろわないと、そのうち怨まれだってするだろうに」
なかなか触れることのない皮表紙の感触に、ますます慎重になりながら本の重みを大切に抱えたモーリスは、兄の言葉に首をかしげる。
「いつも、妖精は嫌いだと、兄上は言っているよね」
「うん。大嫌いだ。憎いね。だってあれらの厄介な善意とやらのおかげで、寄宿学校にも行けない。陛下への目通りもかなわない。妖精地帯(ここ)から出してもらえない」
「そう、なの?」
「そうだよ。ぜんぶ、善き妖精殿のせい。おまえも憶えておきなさい」
けして、子供の名付け親に妖精を選びなんて、してはいけないよ。
笑んで、声を繋げたトリストラムの、硝子玉のようにどこかつやのないはしばみ色の眸が、言葉とともにわずか細められる。
モーリスにはやはり、兄の無意識のだろうしぐさや、言葉や、声音の意味がよくわからなかった。
「どうして?」
なので、椅子にふかく腰掛ける兄を見上げて、素直に尋ねてみることにする。するとトリストラムは、そうだねえ。と少し考えてからふたたび口をひらいた。
「だって妖精に名もらったおかげで、小妖精がしじゅう、視界の端を横切るよ。一晩中、妖精の輪で踊ろうといって、丘へさらってゆこうとするし。おかげで夜も眠れやしない。領外へ出ようとしたら、俺の乗る馬の足を掴んでくるし」
ひとつひとつおおまじめに挙げることごとは、どうやら冗談ではないらしい。たしかに、トリストラムは三年前に寄宿学校へと赴く途中で、突然の落馬によって足を悪くしている。兄がよく日中も臥しているのは、彼が虚弱であるからだとモーリスは聞いていた。けれど――もしかすると、それらはほんとうに、モーリスには見えない、触れられない、声すら聴けない妖精たちのせいなのかもしれない。
急になにやら恐ろしくなって、でも、と少年は兄に問うた。
「でも、妖精の名付け親は、気にいった子供に名前をつけるんでしょう? それで、守ってくれるんでしょう? それなのに、なんでそんなこわいことをするの」
すると、トリストラムは一度またたいてゆっくりと、いまはモーリスの抱える本に指を伸ばして言う。
「ながく生きると、どうやらね。気にいったものは、手元において手放したくなくなるらしい」
そうして本の小口に連なる物語の題名、そこにふくまれる主人公の名に触れると、トリストラムはそっとモーリスの手から重みを取り去った。
「しっている? モーリス」
己と同じ名前の騎士の物語を、陽光まばゆいばかりの窓辺へあえて置くと、このうえもなくしあわせそうに、トリストラムは外の景色へ視線を遣った。
「妖精殿が俺にくれた名前はね、悲しみの子という意味なのだそうだよ」
兄につられて、モーリスが窓辺の硝子の向こう側を見下ろせば、妖精地帯とあだなされるアディンセル伯爵領の、曇りがちな空と丘陵が、風の下に続いていた。
結局。外の世界をみつめつづけたトリストラムが、若くして死を迎えたのは、それからわずか三年後のこと。
後に兄に代わって爵位を継ぐこととなるモーリスが、霧の都のほどちかくにある寄宿学校へと赴いた、その翌日のことだった。