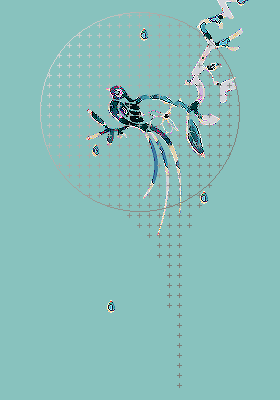
じわりと雨の気配のきざす、空のわずかよどんだその日。とうとう、長のすすめによって、わたしの婚礼がまとまった。 |
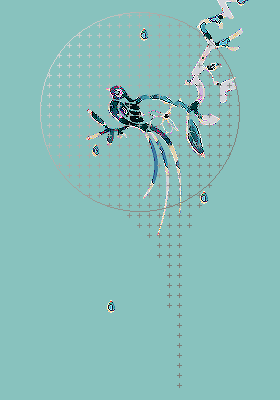
唐突にもたらされた変化に、わたしはすこしばかり臆しもした。 なにせ、うだるように湿る空気が身を蝕む、初夏を迎えたばかりのその頃、わたしはまだ十五を数えたばかり。それも、いまは家を離れた双子の兄に頼りきってばかりいた、こどもめいた娘だったのだ。 婚儀の相手は近しい国の豪族で、海辺の氏族の長の甥である。 世には戦の気配もあるが、おまえの夫となるのは我ら 正直わたしは、今でもこの話に乗り気というわけではない。しかしわたしも相手も、それぞれの氏族の長筋の者だ。長たちにとってもつりあいもとれた、良縁なのだとは考えた。 結局、正式に話がまとまった時も、とうとうわたしも、誰かと 以来、母がわたしに笑いかけることが多くなった。一昨年に父を亡くしてからこちら、ふさぎこむことの多かった母の、ひさかたぶりの笑顔である。それを曇らせるのはやはりはばかられたから、わたしは特に彼女に内心を示すこともなく、淡々と日々の仕事に精を出した。 同年代の娘たちからは、祝いの言葉、羨望のまなざし、嫉妬の声、あらゆるものが寄せられた。若い男衆からは、きっとわたしの双子の兄との確執もあるからだろう。あいかわらず、これといった干渉もなかった。 ただ一度、様子からして市へ出向いた帰りであろうか、若衆の一人と道でゆきあった時に「 陸弥が、わたしの双子の片割れが帰ってくるかもしれないと。その報せは、婚礼の話以上に、わたしに驚きとよろこびをもたらした。父が亡くなってからわずか半年のうちに、まほろばの都へと発っていって以来、一度も帰郷していなかった陸弥。 以前に一方的にもたらされた報せによれば、彼はいま、大王の血を継ぐ皇子のひとりに仕えているのだという。けれど近々この地に帰ってくるやもしれないならば、もしかするとわたしの婚礼にもまにあうかもしれない。 わたしはそのうれしい報せを、その日のうちに母に伝えた。母はこどものようにはしゃぐわたしに呆れたのか「よかったわ。でも、あなたも夫を迎える身なのだから」と、曖昧に苦笑しただけだった。 今にして思えば、母はわたしたちが幼い頃より、陸弥の存在を持て余していたのかもしれない。 なにせ、陸弥は獣だ。 いくらわたしと陸弥がただしく対の双子であろうとも、わたしが追いすがり続ける陸弥はたとえるなら、凛としなやかな獣である。そして皇子に仕え、その配下として繋がれるまで、彼はまさしくまつろわぬ、牙をふりかざした手負いの獣だった。 獣である陸弥にとって、それはすべて本能であったのだろう。 幼子の時分より人になつくこともなく、暖かな手で育まれることも拒み、長じて後も誰となれあうこともなく。そうしてやがて、己を取り囲むものすべてに抗うようにして、たったひとりで少年へと孵化していった陸弥は、わたしにとってかけがえのない双子の対であった。 けれど母にとっては、その手を必要とすらせずに、どこまでも高い場所へ巣立っていった息子であった。 母が陸弥と距離を置くことも、仕方のないことなのかもしれなかった。 さて、報せのとおり、夏のさかりの頃に、陸弥はわたしのもとへ帰ってきた。やはり、主である皇子が近くまでいらしているため、随行している従者の一人である陸弥は、いっときではあるも、故郷へ赴くことを許されたのだという。 道まで飛び出して出迎えたわたしへ、彼は簡潔にそう説明し「やはりおまえも、相変わらずだな」と、きつく笑ってわたしの髪をくしゃりとなでた。 「陸弥は、背も高くなったのね。それに、立派な剣をいただいたんだね」 「まあ。皇子のお役に立つのに、必要だから」 「いまは、皇子の近習を務めているんだ。剣をいただいたのは、そのせいもある」 彼の帰郷によろこびを隠さないわたしの、一瞬の興味を汲みとって、陸弥は口の端でかるく笑みをかたちづくって言った。 夏の日差しの燦として降りそそぐ道を、ふたりで歩きながら、家へ向かうその間。わたしたちはぽかりと空いた時間を埋めるかのように、あれこれと言葉を交わしつづけた。 そしてやがて家が見えるころ、わたしはふと思い出して「そういえば」と陸弥を見上げる。 「わたし、この夏の終わりに夫を迎えるよ。縁続きの氏族のひと。陸弥も、都でだれかよい人はいた?」 「――は?」 瞬間、彼はまるで凍てついたような、冷やかな視線でわたしを切り裂いた。 驚きたじろいだわたしの左手を、乱暴にとりあげて彼は「なんで」ときつく続ける。 「長が。話を持ってきて、とりまとめたの」 「夫を迎えるって。どうして、いま」 「だって、陸弥は皇子さまに仕えているじゃない。そう、たやすくたよりは出せなかった」 「おまえは……好いて、婚礼を? 氏族だって異なるだろうに」 苛立ち、次々と言葉の刃を突き付けてくる陸弥の声は、手負いの獣のように荒れていた。それはまるで、拾われたばかりの幼いころのように。 どうしてわたしに、またそんなに恐ろしい態度をとるのか。せっかく、また会えたのに。わたしはわたしでそう苛立って、冷静さを装いながらも、一気にまくしたてて返す。 「好いたわけではないけれど。でも、長も母上も乗り気だし。氏族だって、父上と母上も、出自は違ったよ。それにつたえのひとつも送れないからといって、知らないあいだに双子の妹が嫁いでいたなんて、陸弥だっていやでしょう?」 「……まだ、そんなものにしがみついていたのか」 ひくく、ひくく、陸弥は残酷に言った。とりあげていた私の左手も乱暴に手放す。一瞬、燃えるように陽のさんざめく空の冴えたいろよりも、はるかに彼を遠く感じた。 「そんなもの。拾われ子がうそぶいた、こどもの戯言だろう。兄妹だの、双子だの――馬鹿か」 ゆっくりと、わたしは目を見開いて。みたことがないほど冷たく怒る陸弥が、わたしたちの育った家の中へと消えるのを、陽炎越しに見送った。 ――くるしいと、からだが悲鳴をあげてから気づく。呼吸さえも忘れていた。 しっている。 陸弥とわたしは、互いを対と呼びあえるような血のつながりなど、もってなんかいない。 いつかの大きな戦の折に、父はまだ幼い彼を、わたしたちのもとへ連れてきた。陸弥を息子として育てることが、同じ戦で血縁筋の氏族のあらかたを滅ぼされた、父のつよい願いだった。 けれど。たとえ血のつながりがなかったとしても、拾われ子の陸弥とわたしは、双子だ。対の人間だ。 絶対に、相手が欠けては生きてなどいけないと言えるくらいに、それは確かなこと。 それは幼い日に陸弥が言ったことだ。わたしが信じ続けたことだ。だというのに、彼はどうして、それを切り捨てたのだろうか。 たとえるならば、幼いころよりただしく、まつろわぬ獣だった陸弥。主を定めず、求めもせず、刃を抱いて傷を鎧っていたわたしの片割れ。 もしかしたら、彼はもう、わたしの隣にいた陸弥ではないのかもしれない。 陸弥がまほろばの都へと発った日から、憂えるように感じていたおそれが、そっと影を落としこむ。 剣の力も祭りの力もたったひとりであわせもつ、偉大な大王の支配の下へと参じた彼は。やがてその王権を受け継ぐ皇子に仕えてしまった彼は。もう、わたしなどいらないのだろうか。 その血縁を対の繋がりと見なして、兄と妹が剣と祭りを分け持って統べるこの地で。わたしと陸弥が、そのとおりに兄と妹であろうと交わした約束。その 恐ろしくなって、わたしは家の中へと彼を追った。 けれど追いついてももう、彼はなにかを決めたように、わたしにはいっさい眼差しをよこさなかった。 ただ養い親である母に挨拶をし、わたしとは当たり障りのない言葉だけを交わし。凍てついた視線もとかさぬままに、夜も更けぬうちにと言って、陸弥は早々に皇子のもとへと帰っていった。 この夏が終われば、わたしは見知らぬ男と婚う。 でも、わたしと陸弥がただしく双子であったのなら、陸弥がわたしを妹と呼んでくれたのなら。たとえわたしが人の妻となったって、その絆は変わらないはずだった。 剣と祭りの結びつきは、えてしてそういうものである。わたしたちは、別々に死んで、別々につちくれへ還ってさえも、対でいられるはずだった。 けれど陸弥はわたしを拒み、まほろばの剣をたずさえて去り。わたしはこの地に、約束ごと、思い出ごと、絆ごと、たやすく捨て去られたのだった。 炎天のもと、陽炎の向こうと、こちらへ。わたしたちは確かに切り離された。 その夜、わたしは初めて、ひとりきり涙を流した。 幼子として泣きわめいた頃とは違い、かたわらに対の彼のぬくもりはない。 つまり、陸弥は。 わたしの大切な陸弥は、きっともうどこにもいないのだ。二度と、わたしのもとへは帰ってはこない。 どうして、わたしたちは対としてうまれてはこられなかったのだろうか。 陸弥。ただひとりの、わたしの片割れよ。 あなたと、つがいでありたかった。 ――そうして、夜明け近くまで。いつかの幼い日々、夜ごと陸弥とともにとなりあって過ごした寝所でひとり泣いて、泣いて。わたしは暁のまどろみの中で、家の外に降りたったざわめきを聞きながら、眠りの中にしずみこんだ。 今までにまみえたことのないような、多く聞こえくる馬のひづめの音にも、鉄の打ちあわされる響きにも、家を囲む大勢の人の気配にも、意識を奪われぬままに。 やがて、泣きはらした枕辺に、たったひとり愛おしくおもったひとが、その手の剣を抜き放ち、訪れるとも知らないで。 |